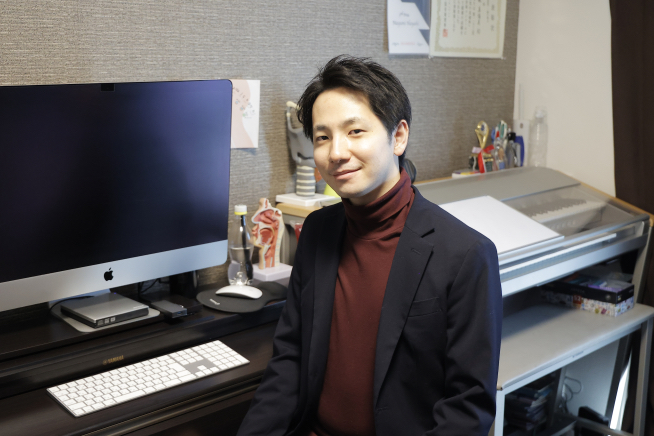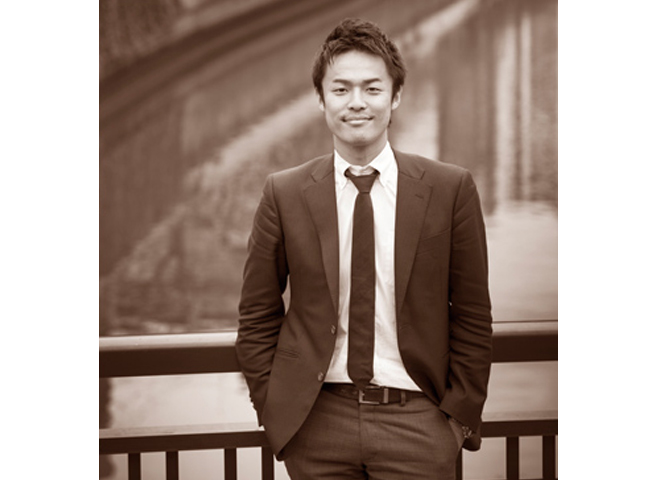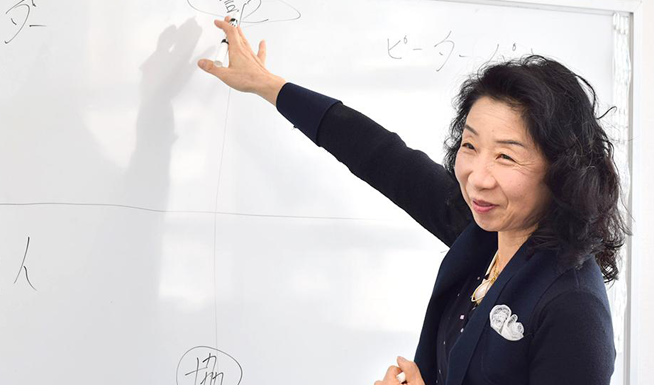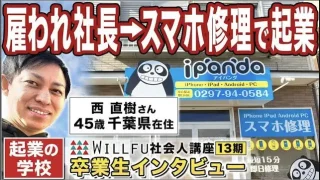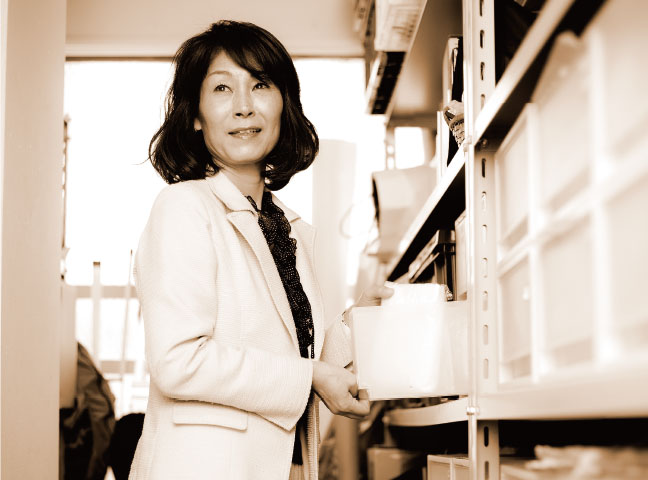「副収入は欲しいが、会社で副業が禁止されている」と悩む会社員の方は多いでしょう。
その解決策として注目されるのが投資です。多くの場合、投資は労働の対価である副業とはみなされず、資産運用として扱われるため、就業規則に抵触しにくいのが特徴です。
本記事では、副収入を得たい会社員に向けて、以下の点を徹底解説します。
- 投資が副業にあたらない理由と法的な違い
- 会社に知られずに投資を続けるための注意点(住民税対策など)
- 初心者でも少額から始められるおすすめの投資方法
- 投資で利益が出た場合の税金(確定申告)の基本
本業に支障なく、不労所得の土台を作りたい方は、ぜひご一読ください。
投資は副業にあたる?会社にバレないための注意点
投資が会社にバレることを心配する方は多いですが、投資は副業とみなされないケースがほとんどです。
ここではその理由と、会社に知られずに続けるための具体的な対策を解説します。
投資と副業の法律上の違いとは?
株式投資や投資信託などは、原則として副業に該当しません。
法律上、この二つは明確に区別されます。就業規則で副業が禁止されていても、投資は資産運用の範囲内と解釈されるのが一般的です。
ただし、FXの短期売買のように、勤務時間中に頻繁な取引が必要なものは「本業に支障が出る」とみなされ、問題となる可能性があります。
重要なのは、「会社にバレるか」よりも「本業の勤務に支障が出ないか」という視点です。
【要注意】投資が副業とみなされる・禁止される例外
原則として投資は資産運用ですが、以下のようなケースでは就業規則違反や法律違反とみなされる可能性があります。
1.本業への支障が認められる場合
勤務時間中に頻繁に株価をチェックしたり、FXのデイトレードに没頭して業務に支障が出れば、懲戒処分の対象となり得ます。
2.社内規定で明確に禁止されている場合
特に金融機関では、インサイダー取引(未公開情報を使った不公正な取引)を防止するため、自社や取引先の株式売買を厳しく制限していることが一般的です。
3.公務員の場合(規模の制限)
公務員も原則として投資は可能ですが、例えば不動産投資においては5棟10室以上など一定規模を超えると事業とみなされ、許可が必要になる場合があります。
会社に知られず投資を続けるための3つの工夫
会社に投資を知られる主な原因は住民税の通知です。以下の3点に注意すれば、リスクは最小限に抑えられます。
1.住民税の徴収方法で普通徴収を選ぶ
投資で利益が出た場合、確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収に指定します。これにより、投資の利益分の住民税通知が会社に行かなくなり、会社に知られるリスクを減らせます。
※NISAや特定口座(源泉徴収あり)を利用する場合、原則として確定申告は不要です。
2.確定申告を正しくおこなう
源泉徴収なしの口座で一定以上の利益(会社員は年間20万円超など)が出た場合、確定申告が必須です。申告漏れは後に大きな問題となるため、ルールを正しく理解しましょう。
3.SNSでの発信に注意する
投資で儲かったなどの内容を、勤務先が特定できるようなSNSアカウントで発信するのは非常に危険です。不用意な投稿から、会社に知られるケースは少なくありません。
会社員におすすめの投資とは?副業と両立できる運用方法
本業で忙しい会社員が副収入を得るには、時間や手間がかからない投資方法を選ぶことが重要です。
ここでは、無理なく両立できる運用スタイルを紹介します。
少額で始められる投資タイプ
投資にはまとまった元手が必要と考えるかもしれませんが、現在は数千円、あるいは100円からでも始められる投資商品が増えています。
つみたてNISA(積立NISA)
少額から長期的な積立投資ができ、利益が非課税になる国の優遇制度です。
金融庁が選んだ比較的リスクの低い投資信託が対象で、初心者にも適しています。
ロボアドバイザー
AIが自分に合った資産配分(ポートフォリオ)を自動で提案・運用してくれます。
専門知識がなくても、リスクを分散した国際的な投資が可能です。
忙しい社会人でも続けられる投資習慣
会社員が目指すべきは、日々の値動きに一喜一憂するスタイルではなく、放置型自動化の投資です。
インデックスファンドの自動積立
特定の市場指数(例:日経平均やS&P500)に連動する投資信託を、毎月決まった額で自動的に買い付ける方法です。
一度設定すれば手間がかからず、長期的な資産形成に向いています。
不動産クラウドファンディング
1口1万円程度から不動産へ間接的に投資できる仕組みです。物件の管理・運用はプロ(運営会社)に任せられるため、時間的な負担が一切ありません。
自動化された仕組みを活用することで、本業に集中しながら副収入の土台を築くことが可能です。
投資で副収入を得る際の注意点とよくある失敗例
副収入目的で投資を始めても、知識不足から資産を減らしてしまうケースもあります。
事前に典型的な失敗例とリスクを学び、大切な資産を守りましょう。
ありがちな初心者のミスとは?
初心者が陥りがちな失敗は、主に早く稼ぎたいという焦りから生じます。
1.一攫千金を狙う
「SNSなどで爆上がりした銘柄」といった情報に飛びつき、高値掴みをして損をする典型的なパターンです。
2.他人のおすすめを鵜呑みにする
投資は自己責任です。他人の推奨をそのまま信じ込まず、自分でその投資が本当に妥当か理解し、納得するプロセスが不可欠です。
3.一極集中投資
資産を一つの商品(例:特定の企業の株式)に集中させると、その価値が暴落した際に全資産を失うリスクがあります。
投資詐欺に引っかからないために
近年、「誰でも簡単に稼げる」となどの甘い言葉で勧誘してくる投資詐欺がSNSを中心に急増しています。
「元本保証」「絶対に儲かる月利〇〇%」といった非現実的な高利回りをうたう投資話を見かけた場合は、まず詐欺を疑いましょう。投資の世界に絶対はなく、高いリターンには必ず高いリスクが伴います。
どうしても気になる場合は、投資を勧誘する業者が、金融庁の許可を得た正規の金融商品取引業者であるかを必ず確認しましょう。無登録の業者との取引は絶対にしてはいけません。
最大のリスク元本割れを理解する
投資詐欺やミスを避けることは当然ですが、それ以前に投資には元本割れという本質的なリスクが伴います。
元本割れとは、投資した金額よりも、受け取る金額(売却時や満期時)が少なくなることです。
銀行預金とは異なり、株式や投資信託は価格が変動するため、購入時より値下がりすれば損をします。
投資で副収入を得るとは、この元本割れのリスクを受け入れた上で、そのリスクを長期投資や分散投資によって管理し、リターンを狙う行為だと理解しておきましょう。
副収入を得るための方法に“投資”を選ぶ意味とは

副収入を得る手段は様々ですが、投資には他の副業にはない明確なメリットが存在します。
ここでは、そのメリットを深く掘り下げていきましょう。
投資は“副業”にあたらない?
前述の通り、投資は労働ではないため、就業規則の副業禁止規定に抵触しない場合がほとんどです。
会社が副業を禁止する主な理由は、本業への支障や競合他社での労働を防ぐためです。
しかし、投資は(本業に支障が出ない範囲であれば)これらの懸念に当てはまりません。
副業が難しい会社員にとって、投資は就業規則と両立しやすい、数少ない副収入の手段と言えます。
投資は不労所得になりやすい
投資の最大の魅力は、不労所得になりやすい点です。
たとえば、エンジニアやライターなどの副業は、働いた時間や成果物に対して報酬が支払われる労働収入です。また、ブログや動画配信も、継続的にコンテンツを制作・更新し続けなければ収入は途絶えてしまいます。
一方、投資で得られる配当金や、資産価値の上昇による利益は、自分の時間を切り売りすることなく得られる収入です。
本業の時間を確保しつつ、別の収入源を構築できるのが、投資を選ぶ最大の意味です。
投資で副収入を得る前に知っておきたい3つの基礎

投資をなんとなくで始めると、ギャンブルと同じになってしまいます。
ここでは、副収入の柱として育てるために、最低限知っておきたい3つの基本原則を紹介します。
投資はギャンブルではない
投資とギャンブルは根本的に異なります。
ギャンブルは運の要素が強いですが、投資は市場動向や経済を学び、分析することで、利益を得られる確率を高めていく行為です。
運任せにするのではなく、自分自身の知識や努力によって収益の安定化を目指せるのが投資です。副収入を得続けるためには、継続的な学習が欠かせません。
長期投資で複利効果を狙って分散投資もできる
投資の成功確率を高めるためには、以下の3つのキーワードを覚えておきましょう。
長期投資:長期間にわたり同じ金融商品を持ち続けること
複利効果:運用する中で得た収益で再び投資をし、利息が利息を生み収益を膨らませること
分散投資:投資する資産や対象を統一せず、複数の金融商品に投資をすること
これら3つを組み合わせることが、投資で安定した副収入を得るための王道とされています。
流行に左右されない
「今はこれが流行っている」といった情報や、「みんなが儲かっている」という雰囲気に流されて投資するのは危険です。
暗号資産(仮想通貨)のように急激に注目されるものもありますが、その背景にある技術やリスクを理解しないまま飛びつくと、大きな損失を被る可能性があります。
重要なのは、景気や社会情勢など、価値の裏付けとなる要因を多角的に分析し、自分なりの判断基準を持つことです。
副収入に適した投資の条件

会社員が副業として投資に取り組むなら、本業に支障をきたさないことが絶対条件です。FXのデイトレードのように画面に張り付く必要があるものは避けましょう。
副収入を得るために適した投資には、以下の3つの条件があります。
少額から始められる
副収入や投資は、早く始めるほど有利です。特に経験が浅いうちはリスクを最小限にするためにも、少額からスタートできる投資を選びましょう。
投資は元手が大きいほど有利ですが、少額でも長期間続ければ、利益を再投資に回す(複利効果)ことで、資産が増えるスピードを高められます。
拘束時間と労力が少ない
本業がある会社員にとって、使える時間は限られています。
値動きのチェックや取引に時間と労力がかからないようにしなければ、本業に支障をきたしてしまいます。
自動積立や、運用をプロに任せられるタイプの投資の方が、副収入には適しているでしょう。
レバレッジや複利などを狙いやすい
少ない元手や時間で効率よく副収入を得るためには、レバレッジや複利の効果を意識することが有効です。
レバレッジ:手元の資金(保証金)を担保に、それより大きな金額を運用することを指します。FXが代表的ですが、不動産投資におけるローン(借入)もレバレッジの一種です。
複利:利益を再投資することで、資産の増加スピードを加速させることです。
不動産投資でローンを組んで家賃収入を得たり、株式投資の配当を再投資することは、これらの効果を活用する典型例です。
副収入におすすめの投資8選

ここまでに紹介した内容を踏まえ、会社員におすすめの具体的な投資方法を8つ紹介します。
株式投資
企業が発行する株式を購入する方法です。
配当金や株価上昇による売却益を狙って稼ぐ、最もオーソドックスな方法だと言えます。
副収入目的なら、頻繁な売買はせず、配当金狙いで中長期保有するのがおすすめです。
不動産投資
マンションやアパートを購入し、家賃収入を得る投資です。
ローンを利用することでレバレッジ効果が期待できますが、損をしないためには、空室リスクやローン返済のシミュレーションは必須です。
投資信託
投資家から集めた資金を、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券などに分散投資する商品です。
少額から始められ、運用をプロに任せられるため、初心者や忙しい会社員に最適です。
自動化も可能なので、長期的に安定して増やしていきたい方は、投資信託を選択しましょう。
REIT
不動産投資信託のことを指します。
投資信託と同様に、多くの投資家から資金を集めて不動産に投資し、家賃収入や売却益を分配します。
少額で複数の不動産に分散投資できる点や、運用をプロに任せられる点が魅力です。
ロボアドバイザー
AI(人工知能)が、簡単な質問に答えるだけで最適な資産配分を提案し、運用まで自動でおこなってくれるサービスです。
投資知識がなくても始めやすく、手間もかからないため、多忙な会社員に向いています。
外貨預金
日本円を外国の通貨(例:米ドル、ユーロ)に換えて預金することを指します。
日本より高い金利や、為替レートの変動による差益(円安時に利益)を狙います。
為替手数料と、逆に円高になった際の為替差損リスクに注意が必要です。
国債
国が資金調達のために発行する債券です。
購入すると、定期的に利子を受け取れ、満期になれば元本が戻ってきます。
個人向け国債(国内)は元本割れのリスクが極めて低いので、手堅く資産運用したい人向けです。
参照:個人向け国債|財務省
暗号資産(仮想通貨)
インターネット上で取引される電子データ(通貨)の売買で利益を狙う方法です。
価格変動が非常に激しく、ハイリスク・ハイリターンな投資なので、大きな利益の可能性がありますが、副収入の柱とするにはリスク管理が難しいという特徴があります。
まずは少額から試す程度に留めるのが賢明でしょう。
投資で副収入を得たら税金はどうなる?確定申告の基本知識

投資で副収入を得た場合、税金の処理は避けて通れません。
確定申告の基本を知り、安心して副収入を得られる体制を整えましょう。
株式・不動産・仮想通貨それぞれの税区分
投資で得た利益には、所得税や住民税がかかりますが、投資の種類によって税金の計算方法(税区分)が異なります。
1.申告分離課税(株式・投資信託など)
給与所得など他の所得と合算せず、投資の利益だけで独立して税金を計算します。税率は一律20.315%です。
2.総合課税(不動産所得・仮想通貨など)
給与所得など他の所得と合算した総額に対して税金が計算されます。所得が多いほど税率が上がる累進課税(最大55%)が適用されます。
※仮想通貨は雑所得として総合課税の対象です。
節税できるNISAやiDeCoの活用法
会社員が投資をするなら、税制優遇制度を最大限に活用すべきです。代表的なものがNISAとiDeCoです。
NISA(新NISA)
年間の投資枠(つみたて投資枠・成長投資枠)内で得られた投資の利益(売却益、配当金)が非課税になります。
通常は約20%かかる税金がゼロになる、非常に強力な制度です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
老後資金を準備するための制度です。NISAと異なり、掛け金が全額所得控除の対象となります。
これにより、その年の所得税や翌年の住民税が軽減されるという大きなメリットがあります。
これらの制度をうまく活用することで、税金の負担を抑えつつ、効率的に副収入の基盤を築けます。
自己資産に合った投資を選び、少しずつでも副収入を増やしていこう

本業の収入だけでは将来が不安な時代、会社員であっても副収入の確保は重要な課題です。副業が禁止されていても、投資であれば始められる可能性は十分にあります。
ただし、投資には必ず元本割れのリスクが伴います。どのような金融商品でも、絶対に儲かるということはありません。
このリスクを理解した上で、まずは少額から長期・分散を基本に、本業に支障のない範囲で始めてみましょう。REITや投資信託、株式投資などで経験を積みながら元手を増やし、将来の安定した副収入源を育てていくことが、安心への第一歩となります。
<文/ちはる>