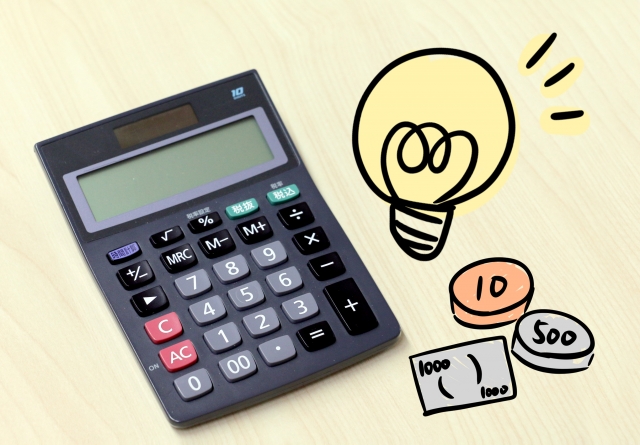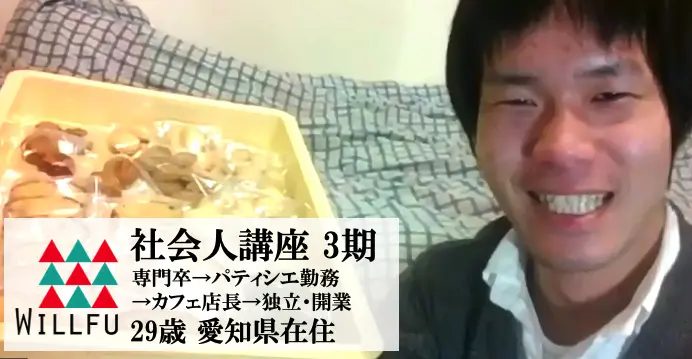フランチャイズの業種の中でも選択肢の豊富さが魅力の飲食系は、生活の一部であり、その身近さから開業を検討する人の中でも人気のある業種です。
今回は飲食店を開業する方法や、飲食店を開業する場合にフランチャイズを活用する方法などを解説します。自分に合う開業方法はどれか、イメージしながら読んでみましょう。
低リスクで飲食店を開く手段『フランチャイズ』とは?

飲食店を開業する方法はさまざまです。しかし、その中でもフランチャイズを利用した飲食店の開業は経営未経験であっても参入しやすく、リスクが低いといわれる開業方法です。
なぜ、フランチャイズを利用すると飲食店の開業はリスクが低くなるのでしょうか?それには、フランチャイズの仕組みが関係しています。ここでは、フランチャイズの仕組みや、フランチャイズを利用して飲食店を開業するメリット・デメリットを解説していきます。
フランチャイズの仕組み
フランチャイズで飲食店を開業する方法を説明する前に、まずはフランチャイズの仕組みについて解説します。フランチャイズとは、フランチャイズ本部である「フランチャイザー」とそこに加盟する個人や法人である「フランチャイジー」により形成されています。加盟店はフランチャイズ本部の保有する「ブランド名や看板を使う権利」や「経営ノウハウ」の使用権に対して加盟金やロイヤリティ(対価)を支払います。フランチャイズ本部の培ったノウハウをパッケージ化したものを活用して事業を展開するのがフランチャイズであり、このビジネスモデルはアメリカが発祥といわれています。
フランチャイズと聞くとチェーン店のイメージを持つ方は少なくないでしょう。しかし、チェーン店には「加盟店」の他に「直営店」もあります。加盟店と直営店の2つには、どのような違いがあるのでしょうか。
まず「加盟店」とは、フランチャイズ本部と「フランチャイズ契約」を交わして経営されている店舗のことをいい、フランチャイジーと呼ばれます。
では、フランチャイズ契約とは、どのような契約になるのでしょうか。
フランチャイズ契約とは、自社の店舗を運営してくれる個人や法人を探している「フランチャイズ本部」と、そのフランチャイズ本部の商号やブランド、商品・サービスを使用して新しくビジネスを始めたいと思っている「個人」や「法人」との間で結ばれる契約です。契約を結ぶことで、そのフランチャイズの商号やブランドを扱う店舗を、個人や法人でも運営できるようになります。フランチャイズ契約を交わす際、加盟希望者はフランチャイズ本部が保有する商号やブランドを扱う対価として「加盟金」や「保証金」を支払います。加盟後は、毎月「ロイヤリティ」として対価を支払わなくてはいけません。
加盟店の責任者は、個人であっても法人であっても、「オーナー」となり店舗の経営者になります。オーナーではフランチャイズ本部に雇用されているわけではないので、基本的に何かあった際の店舗の全責任はオーナーである自分のものであると覚悟しておくようにしましょう。
それに対して直営店は、別名レギュラーチェーン(RC)と呼ばれます。フランチャイズチェーンを運営する企業が自社で直接、運営している店舗を指します。直接、フランチャイズ本部に雇用されている人が「店長」という役職に就いて直営店の責任者となっているケースがほとんどです。加盟店のオーナーという経営者のポジションとは異なり、一社員であるため何か不祥事があった際にも全責任を問われることはまずないと考えて良いでしょう。
こちらの記事では、フランチャイズについて初心者向けに解説しています。
https://entrenet.jp/magazine/25755/
飲食業のフランチャイズに加盟するメリット

飲食業の中にもフランチャイズはたくさんあります。「自分の憧れのお店を持ちたい!」と思って飲食業の開業に憧れる方も多いのではないでしょうか。しかし、自分で開業するよりもフランチャイズに加盟をした方がメリットは大きいと感じる方も少なくはないでしょう。
飲食業におけるフランチャイズに加盟するメリットは、主に以下の5つです。
フランチャイズで飲食業を営む際のメリットについて、それぞれ解説していきます。
商品開発や仕入れ先の開拓をフランチャイズ本部に任せることができる
フランチャイズならではのメリットの1つ目は、商品開発や仕入れ先の開拓などの業務は、フランチャイズ本部にまるまる任せられる点です。
既存の商品はもちろんのこと、季節やトレンドに合わせた新商品の開発、それに合わせた良質な食材やその仕入れ先の開拓・交渉は、本来であれば膨大な時間や労力が必要です。メニューや商品開発はただ「どのような商品だったら売れそうか」を考えるだけではなく、実際に食材を使って試作品を作ってみたり、食材や調理道具や食器の仕入先といった提携会社を探したりなど大きな工数がかかります。
しかし、フランチャイズであれば、これらの開発業務をフランチャイズ本部に任せられるため、加盟店のオーナーは店舗運営に集中することができます。
経営未経験でも安心して経営に臨める
フランチャイズならではのメリットの2つ目は、経営未経験でも安心して経営に臨める点です。
フランチャイズとはいえ、フランチャイズ契約をするとお店の「オーナー」、すなわち経営者になることになります。「経営の知識やノウハウがないと経営者になれないのではないか」と不安に感じている方も少なくはないでしょう。
しかし、フランチャイズ契約をすると、商品や仕入れ先の提供にとどまらず、経営ノウハウやマニュアルをフランチャイズ本部から共有してもらえます。そのため、自分自身に飲食業界の知識や経験がなかったとしても、パッケージ化されたノウハウがあれば、ある程度のことは乗り切れるようになるでしょう。もちろん、自分では何も勉強しない、知識を身につけないで良いというわけではありません。しかし、開業するにあたって必要な知識やノウハウの共有や研修なども受けられますし、不安な点はフランチャイズ本部の担当者に相談できるので、スムーズに店舗をオープンできるでしょう。
さらに、開業するための支援や継続的なサポートを受けることもできます。そのため「経営どころか飲食業での就労経験すらない」という未経験者であっても安心して開業に踏み切ることができるのです。
ブランド力を活かした集客が見込める
フランチャイズならではのメリットの3つ目は、ブランド力を活かした集客が見込める点です。
フランチャイズ本部には、長年培ってきたブランド力があります。フランチャイズ契約をすると、このブランド力を活用できるというメリットがあります。有名飲食店のネームバリューというのは集客力があり「開店初日から長蛇の列ができる」ということもあり得ます。開店当日にフランチャイズ本部から人材が派遣されたり、店舗支援をするスーパーバイザー(SV)のサポートが得られたりするのも心強いです。
対して、自分で0から開業しようとすると、どうしても知名度がなく集客が思うようにできない可能性がでてきます。集客ができるようになるまで時間がかかってしまっては利益もなかなかあげられなくなってしまうでしょう。集客は利益をあげるのに最も重要になります。そのため、開業当初から集客できるとなれば、開業するにあたってフランチャイズ契約が大きなメリットになるのは明白でしょう。
すでに成功している店舗のノウハウを提供してもらえる
フランチャイズならではのメリットの4つ目は、すでに成功している店舗のノウハウを提供してもらえる点です。
フランチャイズでは、自分以外にも多くの加盟店があります。そのため、加盟店の先輩がたくさんいるというわけです。フランチャイズ本部は経営ノウハウやマニュアルを共有してくれますが、これはあくまでマニュアルです。マニュアルと自分の店舗があまり類似していない場合もあるかもしれません。
そのようなときに役立つのが、すでに成功している店舗のノウハウです。フランチャイズ本部には加盟店から集めた成功事例がたくさんあります。料理の提供スピードや従業員の接客態度など店舗によって工夫されていることもあり、参考になる部分は多いです。成功している加盟店の情報を共有してもらい、自分の店舗を成功させるために活用しましょう。
店舗運営のサポートをしてもらえる
フランチャイズならではのメリットの5つ目は、店舗運営のサポートをしてもらえる点です。
フランチャイズ本部の利益をあげるためにも、加盟店には売り上げをあげて欲しいものです。そのため、フランチャイズ本部は広告の打ち出し方など多角的に加盟店の運営をサポートしています。
また、従業員の募集においても、無名な飲食店だとなかなか応募が集まらないということもありますが、フランチャイズの場合は、ブランド力を活用することで応募者にも仕事のイメージを持ってもらいやすく募集に苦戦することも減るでしょう。もちろん、雇用した後の従業員の教育制度も整っているので、安心して運営できます。
フランチャイズに加盟するデメリット

飲食業のフランチャイズには、メリットだけでなくデメリットもあります。飲食店のフランチャイズにおける主なデメリットは、以下の4つです。
フランチャイズのデメリットについて理解をしておかないと、いざ加盟した後に「こんなデメリットがあるなんて聞いていない!」と後悔してしまうかもしれません。それぞれ詳しく解説していきます。
自分でメニューの開発やアレンジができない
フランチャイズならではの1つ目のデメリットは、自分でメニューの開発やアレンジが一切できない点です。
フランチャイズ契約をして加盟店になると、ブランドのイメージを守ったり、経営効率を向上させたりするために、さまざまな制限が設けられています。「客層に合わせて既存メニューをアレンジしたい」、「店舗オリジナルの新メニューを開発したい」と思っても、フランチャイズ本部の許可が必要となります。勝手に独自のメニューやアレンジを加えたメニューをお客さまに提供したりしてしまうと、最悪の場合は規約違反になってしまったりします。フランチャイズ本部のサポートが充実している一方で、自由度はあまり高いとはいえないでしょう。
競合避止義務がある
フランチャイズならではの2つ目のデメリットは、競合避止義務がある点です。
「競合避止義務」とは、労働者が所属する(もしくはしていた)企業と競合に値する企業や組織に属したり、自ら会社を設立したりといった行為を禁じる内容のものです。
これにより、フランチャイズ契約をしている業界やお店の類似商品やサービスを扱って自分で新しくビジネスを始めることは禁止されています。自分で何か飲食関連のビジネスを始める前の準備段階としてフランチャイズで加盟すると考えている人は、思ったように計画をすすめられない可能性があります。契約内容がどのようになっているのかは、フランチャイズ本部により異なりますので、事前に契約内容を確認しておきましょう。同様の業態でいつかフランチャイズではなく自分一人でイチからお店をつくりたい場合や他にも何か気になることがあれば、合わせてフランチャイズ本部に確認しておくようにしてください。
風評被害を受ける場合がある
フランチャイズならではの3つ目のデメリットは、そのブランド力が故に風評被害を受けてしまう可能性がある点です。
「大袈裟な話」と感じるかもしれませんが、飲食店が提供する商品というのは、場合によって人体に影響を及ぼすことがあります。そして、どこかの加盟店で食中毒被害や異物混入などの問題が発生してしまうと、同じ看板を持つ他の加盟店にも風評被害が及ぶ可能性が非常に高くなるのです。
このような被害の連鎖を防ぐためにも、経営指導をしっかりと行っているフランチャイズ本部を選ぶ必要があります。
ロイヤリティを支払う義務がある
フランチャイズのシステムとはこういうものだ、とわかっていてもデメリットに感じてしまうのがロイヤリティの支払い義務です。
フランチャイズに加盟すると、自分が頑張って売り上げた利益も、全て自分のものになるというわけではありません。フランチャイズ契約を締結すると、共有してもらえるサービスやサポートの対価として、利益の一部からフランチャイズ本部へロイヤリティを支払わなくてはなりません。
ロイヤリティは主に2種類あります。利益の中から定められた割合を支払う「歩合制」と、毎月一定の額を支払う「定額制」の2つです。メリットとデメリットはそれぞれあるので、自分のスタイルに応じてどちらの方が向いているのかよく検討するようにしましょう。
ロイヤリティを支払うとその分、利益も下がり、手取りも減ってしまいます。しかし、フランチャイズ本部の保有するブランドや商品、ノウハウ・サポートを受ける対価になるので、納得のいくロイヤリティの支払い方法を定めているフランチャイズ本部を見つけてみてください。
フランチャイズのロイヤリティについて詳しく知りたいという方は、こちらの記事もおすすめです。
https://entrenet.jp/magazine/25146/
フランチャイズ以外で飲食店を開く方法

飲食店を開業するのには、フランチャイズ以外の方法ももちろんあります。いくつか飲食業を経営する方法を比較して検討し、それでもフランチャイズが良いなと感じたらフランチャイズ契約に踏み切るようにしましょう。他の選択肢を何も検討しないでフランチャイズ契約をしてしまうと、「あのとき、どうしてフランチャイズにしてしまったんだろう」と後悔する羽目になってしまうかもしれません。
ここからは、フランチャイズ以外で飲食店を開業する方法を解説します。フランチャイズとの違いも交えながら解説していくので、開業方法を選ぶ参考にしてみてください。
自分のお店を開く(個人店)

自分でお店を開く「個人開業」は、雇用される側から、自身が事業を経営する立場に変わるということです。
フランチャイズとの違いは、主に次の3つです。
個人で飲食店を開業する最大のメリットは、何といっても自由度の高さです。メニューの開発や営業時間・定休日、店舗のデザインなど、規則に縛られず、自分の好きなように決めることができます。これは、さまざまなルールやマニュアルに沿って運営する必要のあるフランチャイズでは実現できません。しかし、言い方を変えれば「全て自分で決めなければいけない」ということです。事業計画の作成や仕入れ先の確保、宣伝、従業員の雇用など、全てを1人で行うため、時間的な自由は失われる可能性が高くなります。
フランチャイズは、一般的に契約期間の定めがあったり、加盟金・ロイヤリティなどの支払いを求められたりします。一方、個人で開業すれば開業・廃業のタイミングを自分で決めることができます。
また、ノウハウやサポートの提供を受けず基本的に自分の力だけで開業するため、加盟金・ロイヤリティなどを誰かに支払う必要はありません。
個人での飲食店の開業は、フランチャイズと比べ、自由度が高いのが一番の魅力です。しかし、基本的に『業界や経営に対する経験・知識・人脈』などがある人でなければ、失敗のリスクや開業そのもののハードルが高くなります。
ライセンス契約
ライセンス契約とは、商標や特許の権利、ブランドコンセプトなどをパッケージ化して、それらの使用が許諾されるビジネスモデルのことで“パッケージライセンス”とも呼ばれています。パッケージを提供する本部は、ライセンス収入によって収益の拡大を狙います。
フランチャイズとの違いは、主に以下の3つです。
ライセンス契約の場合、著しくブランドのイメージや信用を侵害するようなことでなければ、事業の進め方や運営に関しての規制はほとんどありません。また、ライセンスに関わる事業以外の運営や商品・サービスを取り扱うことにも規制がないので、同じ店舗で並行して事業を運営することもできます。
一方で、フランチャイズのような本部からの支援やサポートは、基本的に行われません。自由度が高い分、さまざまなことを自分で決めて準備していくことが必要なため、経営経験がない人にとっては開業のハードルがあがります。
フランチャイズの場合、月々のロイヤリティや契約期間中の解約に対する違約金の支払いを求められる場合がほとんどです。しかし、ライセンス契約には、ロイヤリティや違約金などが発生しないことが多いです。
また、自由度が高いことから、仕入れ先も独自に探すことができます。本部よりも安価な仕入れ先と取り引きができれば、運営コストを大幅に抑えることが可能です。
ライセンス契約は、フランチャイズと比べ「自由度が高く運営コストを抑えられる」ので「業種や経営に対してある程度の知識や経験がある人」にとってはメリットが多く、事業の成長にもつながるビジネスモデルといえるでしょう。
のれん分け
のれん分けとは、店舗の従業員が独立し新たにお店を始めるときに、もともと働いていた店舗の名前や商品を使用する許可を与えられることです。
フランチャイズとの違いは、主に以下の4つです。
のれん分けの大きな特徴は、契約関係がないということでしょう。また、のれん分けを受ける対象者は従業員または親族である場合が多いです。
のれん分け制度を利用しようという人は、最初から独立することを目的として、店舗で働きながら修業をしています。店舗のオーナーと独立を目指す従業員は、いわば師匠と弟子のような関係です。その弟子がのれん分けをした店舗を開業するということは、師匠に認められたということになります。そのため、のれん分けは師弟の信頼関係のみで成り立っている場合が多く、契約を交わしたり、師匠に対してロイヤリティを支払ったりすることはあまりありません。
また、独立すれば基本的に自分の自由に運営ができます。しかし、師匠との信頼関係あってこその独立であり、師匠の店舗の評判が落ちることのないように独立後も気を配ることが大切です。
さらに、店舗の名前や商品は同じでも、独立すれば別の店舗です。師匠が相談に乗ってくれることもあるでしょうが、基本的には自分の力で店舗を運営し、トラブルにも対応していく必要があります。
一方フランチャイズは、フランチャイズ本部と加盟店が“対等な立場で、ビジネスパートナーになりましょう”という契約を結びます。そのため、のれん分けのように修行期間を必要とせず、短期間で開業ができるのです。短期間で開業したいという人には、フランチャイズの方がおすすめです。
飲食店フランチャイズの3つの開業スタイル

フランチャイズ以外にも、さまざまな開業方法があることを解説してきました。
ここからは、フランチャイズを利用した飲食店の開業スタイルを3つ紹介していきます。
一言でフランチャイズといってもさまざまな形態があります。それぞれのフランチャイズの特徴やどのような人に向いているフランチャイズなのかについても解説していくので「フランチャイズを利用する・しない」「自分に合ったフランチャイズ飲食店の開業スタイルはどれか」など、イメージしながら読んでみてください。
【未経験から開業したい人におすすめ】フランチャイズチェーン
未経験から開業したい人におすすめなのは「チェーン」です。チェーンとは、フランチャイズチェーンのことです。
ファーストフード店やカフェ、焼き肉店などは、チェーン店の場合が多いです。街中で同じ看板を度々見かけるなら、そのお店はチェーン展開しているかもしれません。
フランチャイズチェーンは、フランチャイズ本部から提供される商品、経営ノウハウ、マニュアルなど、一連のビジネス展開に必要なものをパッケージとして提供してもらえます。経営未経験から飲食店を開業したい人にとっては、これほど心強いものはないでしょう。
また、最も重要なのは、ビジネスパートナーとなるフランチャイズ本部の選び方です。フランチャイズ本部が提示する契約の内容は、フランチャイズ本部によって多種多様です。
例えば、デメリットとしてあげられる加盟金やロイヤリティなどの支払いですが、ブランドの知名度が高いフランチャイズ本部では加盟金やロイヤリティの支払いがなかったり、ロイヤリティが低く設定されたりしている場合があります。
飲食業での就労経験や経営経験がないとしても、フランチャイズを利用して開業するならば、その仕組みや契約内容への理解を深めることは大切です。自分にとってのデメリットや不安を解消でき、信頼できるフランチャイズ本部を選ぶ力をつけましょう。
【すでにお店を持っている人におすすめ】併設
すでにお店を持っている人におすすめなのは「併設」です。
併設とは「今あるお店の業態を変更せず、店舗の空き時間やスペースを活用して業態をプラスすることで、売り上げアップを目指すビジネスモデル」を指します。
飲食店では、弁当の製造や宅配ビジネスなどがあります。もともとレストランやカフェを運営しているお店であれば、厨房スペースを有効活用し、客席スペースを圧迫することなく売り上げにつなげることも可能です。
またフランチャイズの「業界未経験者でも参入しやすい」という特性を活かすことで「本屋×カフェ」「美容院×レストラン」など異業種同士を併設することもできます。
すでにお店を持っている人でも業態や事業を多角化することで、消費者のニーズに幅広く対応したり、もともといた顧客の来店率を向上させたりできます。「今よりも経営を安定させたい」「今のお店を経営しながら、新規事業に挑戦したい」という人は、利用を検討すると良いでしょう。
【自由にやりたい人におすすめ】フリーネーム
自由にやりたい人におすすめなのは、「フリーネーム」です。
フリーネームとは、屋号(店名)を自由につけられるフランチャイズです。
フリーネームフランチャイズは、お店の名前だけでなく、店舗づくりやメニューの考案も自由に行えます。一見するとフランチャイズとは思われず、店舗が有名になってくると、唯一のお店として認知される可能性もあります。
さらに、フランチャイズ本部によっては、ロイヤリティが0円というところもあります。
また、飲食業のフリーネームフランチャイズでは、フランチャイズ本部から店舗で提供する商品の材料やレシピが提供されます。フランチャイズ本部にもよりますが、提供される商品は調理の経験がない人でも作りやすいよう簡易調理できるものが多く、飲食業未経験者でも参入・成功しやすいシステムになっています。
フリーネームフランチャイズは、まさに「個人開業とフランチャイズの良いとこ取り」といえるシステムです。「フランチャイズに興味はあるけど、いろいろ自由にやりたい」という人にとって、メリットの多いシステムでしょう。
ただし、商品の提供はあっても、経営に関するサポートが見込めない場合があります。また、ロイヤリティは0円でも、加盟金や保証金が高額というところもあります。フリーネームフランチャイズを利用する場合は「フランチャイズ本部から何のサポートが受けられるのか」「フランチャイズ本部へ支払うものはどのようなもので、金額はどれくらいなのか」を確認し、自分の希望に合うフランチャイズ本部を見つけることが重要です。
飲食店フランチャイズの資金繰り
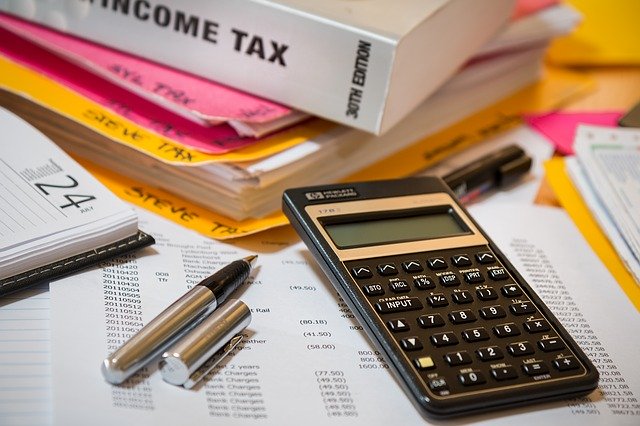
ここまで、フランチャイズ飲食店の開業スタイルを紹介してきました。自分に合いそうなフランチャイズはあったでしょうか。
ここからは、フランチャイズを利用するにあたり「開業資金はどれくらいかかるのか」「フランチャイズに加盟すると、融資に影響があるのか」について解説します。開業するためには誰もが考えなければいけない資金繰りですが、情報を得ることで悩みが解決できるかもしれません。
開業資金はどのくらい?
「フランチャイズ・チェーン事業経営実態調査 報告書 平成 20 年3月」(出典:経済産業省 商務情報政策局 サービス政策)によると、飲食店(外食業)の開業で必要な開業資金の平均額は以下の通りです。
飲食店フランチャイズでは、他の業種と比較して開業資金が多額になるケースが多いです。理由としては、他の業種よりも規模の大きな店舗を必要とすることが多く、それに伴う物件の取得費や内装費などがかかってくることが主な原因と考えられます。
一般的に、店舗を自分で用意するよりも、フランチャイズ本部に用意してもらう方が開業資金は低くなります。開業資金を抑えたい場合には、店舗をどちらが用意するのかをフランチャイズ本部に確認したり、無店舗型のフランチャイズを検討したりすると良いでしょう。
参照:フランチャイズ・チェーン事業経営実態調査 報告書 平成20年3月|経済産業省商務情報政策局サービス政策(P.19より)
※リンクの遷移先はPDFです。ダウンロードに大量の通信費がかかる可能性があります
融資への影響は?
飲食系のフランチャイズで開業する場合、多額の資金が必要になることから、融資を利用するケースも多くなると思います。では、フランチャイズへの加盟は融資に影響するのでしょうか?
結論からいうと、フランチャイズへの加盟が融資に影響することはありません。
しかし、これはあくまで『融資判断』の話であり、場合によってはフランチャイズが原因で融資がダメになってしまうことがあります。
なぜかというと、フランチャイズのような事業においては、フランチャイズ本部の経営成績や信用問題が審査での重要な項目になってくるからです。そのため、そもそもフランチャイズ本部側に経営不振や金融関係の信用を裏切る行為(延滞、過去に破産や民事再生などを行っているなど)がある場合には、加盟者についても融資をしないという判断になる可能性があります。
フランチャイズ本部と加盟店というのは、一蓮托生の関係と判断されます。そのため、フランチャイズ本部を選ぶ際には「本当に安全なフランチャイズ本部なのか」「財務や信用面に問題がないか」についても忘れずに確認してください。
自分に合ったフランチャイズを活用しよう!

今回は、飲食店の開業にフォーカスして、フランチャイズの活用方法や開業方法などを解説してきました。
経営経験が全くないという人は、フランチャイズに加盟することで、安心して開業に踏み切ることができるでしょう。経営の経験がある人は、ライセンス契約やフリーネームフランチャイズを利用することで、自分らしさを活かした飲食店の開業を目指すことができるでしょう。
まずは、どのようなフランチャイズ本部があるのか、見てみることから始めてはいかがでしょうか。
<文/ちはる>