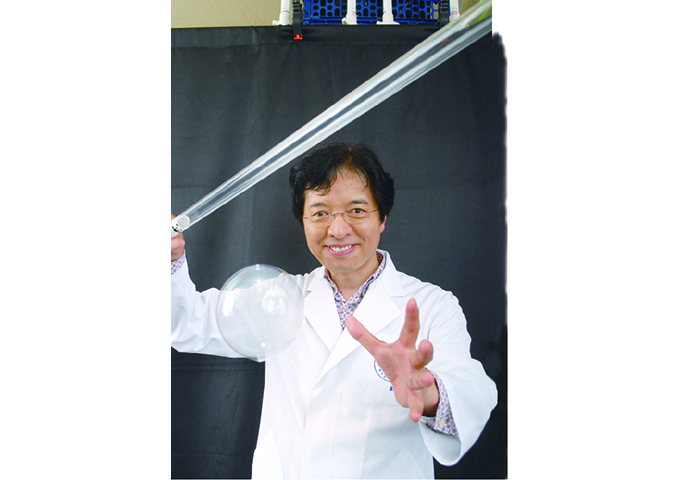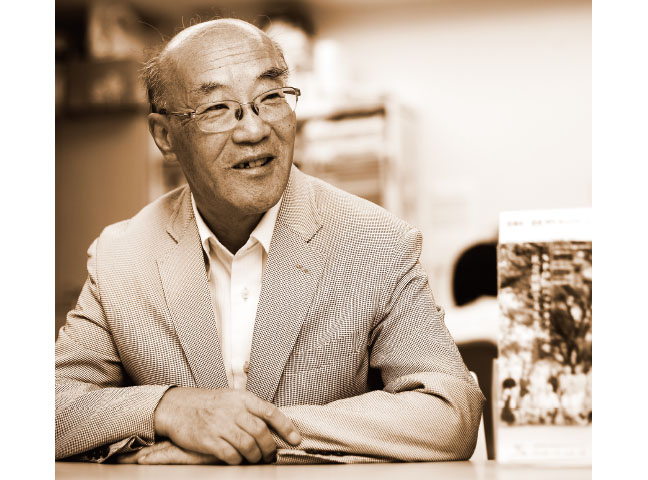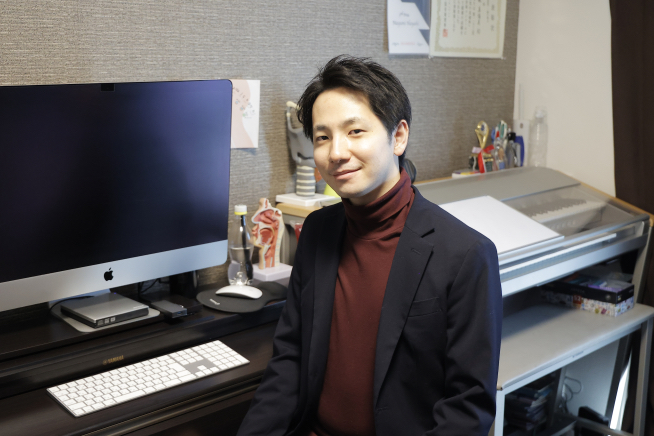個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営む働き方を指します。
開業届を提出するだけで誰でもなれると思われがちですが、実は環境や条件によって「なれない人」や「認められないケース」が存在することをご存知でしょうか。
本記事では、個人事業主になれる人・なれない人の条件、副業収入があっても認められないケース、個人事業主のなり方について解説します。
個人事業主とは

個人事業主とは法人を設立せず、個人で事業を営む人のことです。税法上は税務署に開業届を提出した上で事業を営む人を個人事業主として扱います。
個人事業主の仕事を本業とするケースもあれば、会社員として働きながら副業で個人事業主になるケースもあります。
個人事業主とフリーランスの違い
フリーランスとは会社や組織に所属せず、個人で仕事を受注する働き方を意味する言葉です。働き方の呼称であり、法的な区分が存在するわけではありません。
個人事業主は事業を営む個人を指す言葉であり、税法上の区分でもあります。個人事業主は事業形態の一種といえるでしょう。
一方で、前述のようにフリーランスは事業形態ではなく働き方を意味する言葉です。個人事業主と違い、開業届を提出しているか否かも関係ありません。
個人事業主は事業形態、フリーランスは働き方を意味する言葉の一種となります。
参考フリーランスはスキルなしでもOK?初心者が案件を取る方法5選
個人事業主と自営業者の違い
自営業者は会社や組織に属さず、自ら独立して事業を営む人の総称です。個人事業主だけでなく、自身で会社を立ち上げて事業を行う人も含まれます。
自営業者には事業の代表者や責任者として活動をしている人全体が含まれるため、個人事業主よりも定義が広いです。個人事業主は自営業者の一種となります。
個人事業主になれない人とは

前提として、個人事業主になるための要件は特に存在しません。税務署に開業届を提出すれば誰でも個人事業主になることができます。
ただし勤務先によっては個人事業主になれないケースもあるため注意が必要です。個人事業主になれない人の例を2つ紹介します。
公務員
公務員は原則として個人事業主になることができません。公務員の副業は法律で制限されているためです。
なお一部の自治体では条件付きで公務員の副業を認めているケースがあるため、地方公務員であれば個人事業主になれることもあるでしょう。とはいえ公務員は原則として兼業禁止であり、無断で個人事業主になるのは厳禁といえます。
おすすめ「現役公務員からの独立。フランチャイズを活用し、退職翌月で月商200万超に」岡田悠太郎さん(31歳・千葉県)
副業禁止の会社に勤める人
副業禁止の会社に勤める人も個人事業主になれません。就業規則で副業が禁止されている会社に勤めている場合、個人事業主になると就業規則に反しているとして懲戒処分を受ける恐れがあります。
なお就業規則は法律ではないため、法的な罰則はありません。
個人事業主になれない可能性がある人

続いて、ケースによっては個人事業主になれない可能性がある人について解説します。
未成年者
未成年者の場合、法定代理人の考え方によっては個人事業主になれない可能性があります。
前提として、未成年者が個人事業主として働くことは可能です。事業を営むという行為に年齢はなく、未成年者でも必要な手続きさえすれば個人事業主になれます。
ただし、未成年者が契約行為をするためには、法定代理人の同意や法定代理人を証明する書類が必要です。契約行為に制限があるため、個人事業主として働くことが難しいのが事実です。
なお、個人事業主に法的な年齢制限がなくても、未成年者が個人事業主になるのは法定代理人の同意が前提といえます。個人事業主になることを法定代理人に反対されてしまえば、未成年のうちは個人事業主になるのは厳しいでしょう。
成年被後見人、被保佐人、被補助人など
成年被後見人、被保佐人、被補助人などは、契約をはじめとした法律行為に制限がかかります。いずれの場合も支援をする人のサポートが前提になるため、個人事業主としての活動は難しい可能性が高いです。
副業収入があっても個人事業主として認められないケース

「個人事業主とは」の章で、会社員として働きながら副業で個人事業主になるケースがあると紹介しました。実際に会社員として給与収入を得ながら、個人事業主として副業収入を得るという働き方の人は多く存在します。
しかし、副業で収入があっても、必ずしも個人事業主として認められるわけではありません。
前提として、所得税の対象になる所得は全部で10種類あり、所得の種類によって計算方法が異なります。副業による収入は、事業所得または雑所得に該当します。それぞれの主な特徴は以下の通りです。
| 事業所得 |
|
| 雑所得 |
|
副業が事業所得として認められるのは、副業が独立・継続・反復の要件を満たしている場合のみです。事業が単発で終わる場合や、事業活動の量・収益が少ない場合は事業として認められず、個人事業主になれない可能性が高くなります。
また、以下の2つも事業所得と雑所得を分ける基準です。
- 事業による収入が300万円超であるか
収入金額300万円は事業と称するに至る規模とされ、事業による収入とみなされます - 帳簿をつけており、記帳・帳簿書類を保存しているか
収入が300万円以下でも帳簿をつけている場合は、独立・継続・反復の要件を満たしていれば事業所得として認められます
副業による収入が事業所得ではなく雑所得に該当する場合、個人事業主とは認められません。ただし、税法の区分上の個人事業主になれなくても、副業で収入を得ることはできます。個人事業主になることにこだわり過ぎず、まずは副業に挑戦してみるというのも良いでしょう。
個人事業主になる方法

個人事業主になるまでの流れは大きく5つの工程に分けられます。それぞれの工程について詳しく解説します。
※勤め先や事業の内容によっては一部不要な工程もあるため、自身のケースに合わせて対応してください。
会社に副業の申請をする【一部の会社員】
会社員が副業で個人事業主になる場合、まずは就業規則の確認が必要です。
会社によっては副業をするためには事前に申請が必要なケースがあります。そのため会社員の場合は副業に関する規則を確認し、申請が必要であればまずは副業申請をしましょう。副業申請が承認されてから個人事業主になるための手続きを進めることになります。
なお、「副業禁止の会社に勤める人」で解説したように、副業が禁止されている場合は副業をしない方が良いでしょう。副業をしてしまうと就業規則に反しているとして懲戒処分を受ける恐れがあります。
就業規則で副業に関する規定が特にない場合、会社への申請や報告をしなくても副業できるのが一般的です。当然ではありますが、副業の活動は本業に支障が出ない範囲で行うのが大前提となります。
税務署に必要書類を提出する【全員】
事業所得が生じる事業を開始する場合は、事業開始から1ヵ月以内に開業届の提出が必要です。正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」ですが、一般的には開業届と呼ばれます。開業届の提出は個人事業主が本業か副業かを問わず全員行う必要があります。
開業届の提出先は納税地を所轄する税務署長です。管轄の税務署は国税庁のホームページから確認できます。
開業届の記載項目を紹介します。
開業届とあわせて、提出先が同じ税務署である青色申告承認申請書も提出するのが効率的です。
青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告で行うために提出が必要な書類です。青色申告には以下のようなメリットがあります。
青色申告承認申請書の提出は個人事業主になる上で必須ではありません。とはいえ青色申告には上記のようにさまざまなメリットがあるため、開業届とあわせて提出をし、青色申告者になるのがおすすめです。
インボイスを発行したい場合は、インボイス登録の届出である「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出も必要です。インボイスの届出書を郵送で提出する場合、郵送先は税務署ではなく管轄のインボイス登録センターとなるためご注意ください。
税務署に提出する書類を改めてまとめると以下のようになります。
事業開始等申告書を提出する【全員】
事業開始等申告書とは、個人事業の開始を都道府県に知らせるための書類です。提出先は基本的には都道府県税事務所のみですが、市区町村へも提出が必要なケースがあるため自治体の案内をご確認ください。
書類の正式名称は都道府県によって異なり、「事業開始届」や「個人事業開業届出書」等と呼ばれることもあります。提出期限も都道府県によって異なるため事前に確認が必要です。
事業開始等申告書は、地方税である個人事業税に関する書類です。個人事業税はすべての業種ではなく、地方税法等で定められた業種のみに課されます。そのため、個人事業主でも個人事業税が課されない人もいます。また、個人事業税には290万円の控除があるため、事業所得が290万円以下であれば個人事業税は課税されません。
国民健康保険や国民年金に加入する【個人事業のみの場合】
会社を辞めて起業した場合など個人事業のみの場合は、国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
日本は国民皆保険制度を採用しています。退職して健康保険を脱退したにも関わらず国民健康保険に加入せずにいると、本来の加入日に遡及して保険料の支払いが発生します。保険に加入していないため医療費は全額自己負担になるものの、国民健康保険料の支払いは必要になってしまうのです。
国民年金は全国民を対象とする制度であり、日本に住む20歳以上60歳未満の全員に加入が義務付けられています。加入手続きをせず未納のまま放置していると、将来受け取れる年金が減額されるだけでなく、財産の差し押さえ等が発生する恐れもあります。
退職等により健康保険を脱退した場合、退職日の翌日から14日以内に国民健康保険の加入手続きが必要です。国民年金の手続きの期日も原則として退職から14日以内となります。
国民健康保険の加入手続きでは、健康保険被保険者資格の喪失日等を証する書類が必要です。資格喪失を証明する書類は年金事務所で発行できるため、手元になければ早めに取り寄せましょう。
国民健康保険・国民年金ともに加入手続きは市町村の窓口で行います。自治体によって必要書類が異なる可能性があるため、自治体のWebサイト等の案内をご確認ください。
免許や許認可を取得する【必要な場合】
事業内容によっては免許や許認可が必要なため、営業活動を開始する前に許認可の取得申請を行う必要があります。
許認可が必要な事業の例は以下の通りです。
手続きの窓口は必要になる許認可の種類によって異なります。
許認可を得ずに営業活動をするのは法律違反であり、罰則の対象になる恐れもあります。開業する事業における許認可の必要性を確認し、許認可が必要であれば忘れずに申請手続きをしましょう。
個人事業主に向いている人の特徴

個人事業主には特に要件の定めがないため、必要な手続きさえすれば誰でも個人事業主になることができます。しかし個人事業主は個人で独立して事業を営むという性質上、人によって向き不向きが大きいのも事実です。この章では個人事業主に向いている人の特徴を紹介します。
自分の裁量で自由に仕事がしたい人
自分の裁量で自由に仕事がしたい人は、個人事業主に向いている可能性が高いです。
個人事業主は営業活動から仕事の受注、業務の遂行、納品まですべて自分で行います。請け負う仕事の種類はもちろん、仕事の進め方も自分の自由にできます。
会社員のように企業や組織に所属する働き方では、どうしても個人の裁量に限りがあります。裁量が比較的大きい会社であっても、すべて自分の自由に仕事をすることはできないでしょう。
自由な働き方をしたい人には、個人事業主としての働き方が適しています。
責任感がある人
個人事業主は仕事の種類や進め方をすべて自分で決められると紹介しました。個人の裁量で自由に仕事ができる点は、個人事業主ならではの魅力でしょう。
しかし自由に決められる・自分だけで仕事ができる働き方とは、すべての責任を自分一人が背負う働き方とも言い換えられます。個人事業主には守ってくれる会社や組織が存在せず、仕事の責任はすべて個人事業主本人が負うことになります。
このように仕事の責任をすべて個人で負う性質上、個人事業主という働き方には責任感が必要です。反対に、仕事・役割を全うしようとする気持ちのない人は責任感がなく、個人事業主には不向きと考えられます。
やりたいことがある人
やりたいことがある人も個人事業主に向いている可能性が高いです。
前述のように、個人事業主は仕事内容や受注する案件を自分で決められます。勤務先である会社ではできない仕事を選ぶことや、複数の事業を組み合わせたビジネスをすることも可能です。理念や目標も自分次第となります。
やりたいことが明確な人だけでなく、何か新しい分野にチャレンジしたい人にも、個人事業主が適していると考えられます。
向上心がある人
向上心がある人も個人事業主として適性が高いでしょう。
個人事業主として一人で事業を営む以上、本人の活動の結果がそのまま収入や利益に反映されます。もし売上や利益が低ければ自分で原因を探し、何らかの改善策をとる必要があります。もっと売上を伸ばしたいと考える場合も、目標設定や事業計画の策定などが必要でしょう。このように個人事業主には、売上や利益といった結果を受け止め、その後の事業活動に活かす必要があるのです。
活動の成果が売上・利益といった数字に明確に反映される働き方である以上、向上心が必要といえます。
自分で営業や交渉ができる人
個人事業主は案件獲得や契約内容の交渉なども自分で行う必要があります。
営業活動をせずに待っているだけでは仕事は得られません。特に個人事業主としての活動を開始したばかりで実績がないうちは、案件を受注するために積極的な営業活動が必要です。
案件を獲得するための営業活動だけでなく、交渉が必要な場面も多く存在します。すべて取引先の言われるがままでは、「自分の裁量で自由に仕事ができる」という個人事業主ならではのメリットを得られません。取引先に有利な条件での契約になり、個人事業主側は搾取される一方になる恐れもあります。
営業スキルや交渉スキルは個人事業主に必須といえるでしょう。そのため、自分で営業や交渉ができる人は個人事業主としての適性が高いです。
個人事業主に向いていない人とは

続いて、個人事業主に向いていないと考えられる人の特徴を紹介します。
安定性を重視する人
安定性を重視する人には個人事業主は向いていません。
個人事業主は収入が安定しない働き方です。業種にもよりますが、時期によって仕事内容やスケジュールが大きく異なるケースもあります。また、怪我や病気といった何らかの事情で仕事ができなくなれば収入はゼロになります。
収入や働き方が安定しない点は、個人事業主の最大のデメリットです。そのため、安定を求める人には個人事業主という働き方はおすすめできません。
コミュニケーションが苦手な人
コミュニケーションが苦手な人も個人事業主には不向きと考えられます。正確には、自分から進んでコミュニケーションをとるのが苦手な人には個人事業主の活動は難しいと考えられます。
「個人事業主に向いている人の特徴」で紹介したように、個人事業主は自分で営業活動や交渉などが必要です。すなわち個人事業主の活動ではコミュニケーションをとるべき場面が多く発生します。
コミュニケーション能力が低くても、場数を重ねて経験を積めばスキルが伸びていき、だんだんと営業や交渉が上手くなるでしょう。しかしコミュニケーションに対する苦手意識が強く、積極的な対応ができない場合、そもそも場数を踏めない可能性が高いです。結果として、案件獲得や交渉ができず、事業活動が上手くいかない恐れがあります。
自己管理が苦手な人
自己管理が苦手な人にも個人事業主はおすすめできません。
個人事業主は事業に関する作業をすべて一人で行います。仕事自体はもちろん、優先順位の設定やスケジュール管理、請求書発行などの事務作業も必要です。体調を崩しても代わりに仕事をしてくれる人はいないため、体調管理も必要となります。
納期に遅れず適切に仕事をこなすためには、自己管理を徹底する必要があります。自己管理が苦手な人は、自分一人ですべてをこなす必要がある個人事業主は不向きでしょう。
個人事業主におすすめの職業・仕事

個人事業主は仕事の種類を自由に選べます。資格や許認可が必要な業種もありますが、基本的には好きな職業や仕事を選択できます。
しかし自由度が高いからこそ、どのような仕事をしようか悩んでしまう人も多いでしょう。特に収入アップ等の目的で副業を始めたい人にとっては、副業の仕事選び自体が1つのハードルとなります。
そこで今回は、個人事業主におすすめの職業・仕事を5つ紹介します。
IT関連
IT関連の具体的な職種として、ITエンジニア、プログラマー、ITコンサルタントなどが挙げられます。同じIT系でも、職種や分野によって求められるスキルはさまざまです。
個人事業主にIT関連の仕事がおすすめできる理由として以下の3つが挙げられます。
IT関連の職種の注意点を3つ紹介します。
クリエイティブ関連
クリエイティブ関連の仕事として、デザイナー、イラストレーター、動画クリエイターなどが挙げられます。
クリエイティブ系をおすすめできる主な理由は以下の3つです。
個人事業主がクリエイティブ関連の仕事をする際の注意点を3つ紹介します。
ライター
近年は雑誌や書籍など紙媒体ではなく、Web記事の執筆ライターの需要が非常に高まっています。
ライターをおすすめできる理由は以下の3つです。
ライターの注意点として以下の3つが挙げられます。
通訳・翻訳
通訳・翻訳の仕事は高度なスキルが必要な分、需要が高く案件を獲得しやすい傾向です。
通訳・翻訳をおすすめできる理由として以下の2つが挙げられます。
上手くいけばスムーズに案件を受注できる可能性がありますが、求められるスキルはかなり高めです。また、需要が高いとはいえ他の職種と同様に営業活動の必要はあります。
コンサルタント
コンサルタントはクライアントの相談に乗って、課題の特定や解決のサポートをする職種です。企業の経営に深く関わるコンサルタントもいれば、事業者でない個人をターゲットとするコンサルタントもいます。
個人事業主にコンサルタントの仕事をおすすめできる理由は以下の2つです。
コンサルタントの注意点として以下の2つが挙げられます。
フランチャイズで個人事業主として独立開業もおすすめ

「個人事業主として働きたいけれど、ゼロからすべて自分で始めるのは不安」「独立開業に憧れるけど具体的な仕事内容が浮かばない」このような人におすすめなのがフランチャイズ開業です。
フランチャイズとはフランチャイズ本部である企業に対してロイヤリティを払い、ブランド名の使用権や経営ノウハウの提供を受けるビジネスモデルです。コンビニエンスストアや飲食店、小売店などのさまざまな業種にみられます。フランチャイズ本部をフランチャイザー、加盟店のことをフランチャイジーと呼びます。
フランチャイジーはフランチャイズ本部のブランド名やマニュアルを使用しますが、本部企業の社員ではありません。フランチャイジー自身はあくまでも個人事業主であり、フランチャイザーとはパートナーのような関係となります。
フランチャイズで開業するメリット
フランチャイズで開業する主なメリットは以下の7つです。
フランチャイズは未経験でも開業できるケースが多いです。フランチャイザー企業の方針にもよりますが、対象の業種の経験がなくても加盟できるケースが多くみられます。事前の説明会や研修の制度も整っているため、開業のために必要な知識やスキルはしっかり身につけられるでしょう。
経営ノウハウやマニュアルの提供を受けるため、やるべきことを把握できます。もちろん、売上の向上や経営課題の解決のためには何らかの対応は必要です。とはいえ、少なくとも「何をするべきか全く分からない」「すべて自分で決めなければならない」という事態は起こりにくいでしょう。
前述のようにフランチャイズでは対価としてロイヤリティを払い、ブランド名の使用権や経営ノウハウの提供を受けます。そのため他の個人事業に比べて営業活動や交渉の必要性は低いです。宣伝にコストをかける必要もありません。
本部スタッフによる研修やサポートもあるため、フランチャイジー側は店舗の運営に集中できます。相談するべき相手が明確な点も、フランチャイズ開業ならではのメリットといえるでしょう。
フランチャイズであれば必ずしも成功するとは限りません。しかし、上記のように他の個人事業にはない多くのメリットが存在するため、成功可能性が高いといえるでしょう。
フランチャイズで開業する際の注意点
フランチャイズで開業する際の注意点として以下の3つが挙げられます。
ロイヤリティとはブランド名やノウハウ、サポートの提供の対価として支払う料金です。ロイヤリティの算出方法は大きく以下の3種類に分けられます。
- 売上歩合方式:売上に対して一定の割合を乗じる
- 粗利分配方式:粗利益(販売価格から仕入原価を引いた額)に対して一定の割合を乗じる
- 定額方式:売上や粗利益の額に関係なく、毎月決まった金額を支払う
売上や利益が少ない状態では、ロイヤリティの支払いが負担になる恐れがあります。特に定額方式は、売上等の状況によっては経営を圧迫するリスクが高いため注意が必要です。
自由な事業活動ができない点もフランチャイズで注意するべきポイントです。契約内容に従うのが前提のため、個人事業主ならではの「自由な働き方ができる」というメリットは得にくくなります。
そして一概にはいえませんが、フランチャイズ契約は中途解約ができないケースが多いです。どうしても中途解約をする場合は解約金が発生します。
中途解約に限らず、契約内容に反した場合や本部の指示に従わない場合はペナルティを課される可能性が高いです。理想の働き方をするためには、事前に契約内容を入念に確認した上でフランチャイズ契約を結ぶ必要があります。
参考フランチャイズの仕組みとは?メリット・デメリット・成功事例まで徹底解説
まとめ:個人事業主になれない人のケースや注意点を要確認!

個人事業主になるための要件は特に存在せず、必要な手続きさえすれば誰でも個人事業主になれます。
ただし、公務員や副業禁止の会社に勤める人は副業ができないため、個人事業主になることができません。また、未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人などの法律行為に制限がある人も、個人事業主として活動するのは難しいといえます。
さらに、副業で収入があっても個人事業主として認められないケースがあります。副業による収入が事業所得と認められるのは、副業が独立・継続・反復の要件を満たしている場合のみです。副業が事業所得と認められない場合も、「個人事業主になれない」と表現できます。
個人事業主になることに法律上の制限はありませんが、実際にはさまざまな事情により個人事業主になれない人もいます。後のトラブルを避けるため、個人事業主としての活動を開始する前に、個人事業主になれない人のケースや注意点を確認しましょう。
カンタンに見つかります!

アントレ掲載企業には
週1の副業で月収+16万円の案件も!
今の仕事にプラスアルファするだけで
収入を増やすことも可能です。休日を利用してもOK!
平日の就業後もOK!
空いた時間に働いて
副業で収入を増やしましょう!
無料会員登録で案件を探す