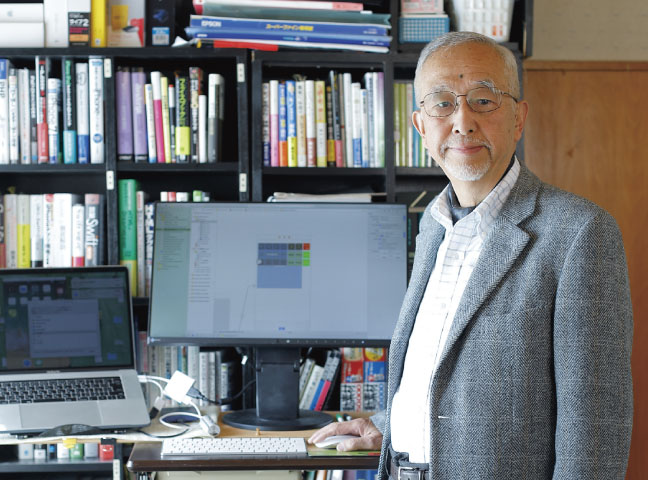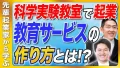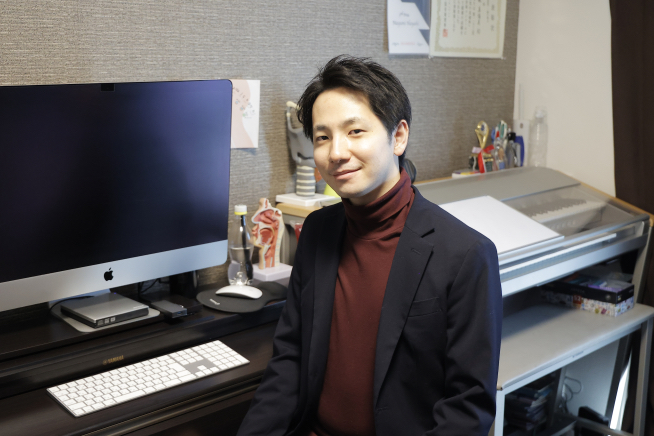昨今、将来への不安から副業を始める人が増えています。
しかし、確定申告が必要になる基準や事業所得と雑所得の違いなど、税金に関する内容に詳しい方は少ないのではないでしょうか。
確定申告を正しくおこなわないと、後から無申告加算税や重加算税が課せられる可能性があるので注意が必要です。
本記事では副業で確定申告が必要になる基準や、その他確定申告にまつわる基本的な知識について徹底的に解説するので、副業を始める方はぜひ最後まで目を通してみてください。
カンタンに見つかります!

アントレ掲載企業には
週1の副業で月収+16万円の案件も!
今の仕事にプラスアルファするだけで
収入を増やすことも可能です。休日を利用してもOK!
平日の就業後もOK!
空いた時間に働いて
副業で収入を増やしましょう!
無料会員登録で案件を探す
そもそも副業とは?

副業とは、本業以外で収入を得るために行う仕事のことです。副業による働き方は法律によって明確に定義されていません。つまり、勤務先が副業を認めているかどうかに関係なく、本業以外で仕事を行って収入を得ている場合は、すべて副業とみなされます。
代表的な副業として、次のような仕事が挙げられます。
このように、自分で商品を仕入れ・制作をして販売する行為やスキルを活かした仕事など、本業の就業時間以外に働くことは副業に該当します。
参考副業はどう始める?スキルを身につけるためのビジネススクールの選び方4選
会社員の副業は確定申告が必要?

会社員の副業で確定申告が必要なケースを詳しくみていきましょう。
副業の所得の合計が20万円以下の場合は確定申告は不要
副業所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告をする必要はありません。これを「副業の20万円ルール」といいます。
副業の所得の合計が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。ただし、厳密にいうと、副業の給与を受け取る事業所が1ヶ所なのか、2ヶ所以上から受け取っているのかによって、細かなルールが異なります。
副業所得を1ヶ所から受けている場合
副業所得を一ヶ所から受け取っている場合は、副業所得が年間で20万円を超えている場合に確定申告が必要です。ただし、収入ではなく、所得金額が20万円を超えているかどうかが基準となる点に注意しましょう。所得金額とは、売上から経費を差し引いたもうけ(利益)のことを指します。
副業所得を2ヶ所以上から受けている場合
アルバイトを掛け持ちするように、副業所得を二ヶ所以上から受けている場合は、年末調整をされなかった給与の収入が20万円を超えていれば確定申告が必要です。この場合は、副業所得を1ヶ所から受けているケースとは異なり、所得金額ではなく、支給金額が20万円を超えている場合に確定申告の手続きが必要となるため、注意しましょう。
給与を2か所以上から受けていて、それ以外の副業もしている場合
給与を二ヶ所以上で受け取っていて、かつそれ以外にも副業をしている場合は、「副業所得を1ヶ所から受けている場合」と「副業所得を2ヶ所以上から受けている場合」のケースを併せて判断しなければなりません。
つまり、年末調整をされなかった給与の収入と、それ以外の副業所得を合計して20万円を超える場合は、確定申告の手続きが必要です。
ただし、一定の条件に当てはまる場合は、確定申告が不要となるケースもあります。確定申告についてわからないことがある場合は、税務署・市町村役場などの公共機関に相談してみましょう。
参考副業の確定申告、20万円の壁を超えたらどうなる?初心者向けにわかりやすく解説!
確定申告が不要でも住民税の申告は必要

副業の所得が20万円以下であっても、居住している市区町村に対して住民税の申告は必要です。住民税には年間20万円以下の所得に対する特例はないため、別途申告しなければなりません。
住民税申告とは、地方税である住民税と市民税の納税額を申告するものです。一方で、確定申告では、国税である所得税の納税額を申告します。
つまり、住民税の申告は、お住まいのエリアの役場に対して行いますが、所得税の確定申告は、納税地を所轄する税務署で行うものです。
住民税申告と確定申告では、提出する申告書の様式や税金の計算方法も大きく異なります。所得税の確定申告のデータをもとに、それぞれの自治体が計算するのが一般的な流れです。
所得と収入の違いとは?

副業をするうえで知っておきたいのが「所得」と「収入」の違いです。それぞれの違いは、次のとおりです。
| 内容 | |
| 収入 | 給与や売上など、1年間に得た金額 |
| 所得 | 収入から、仕入れ額や必要経費を差し引いた金額 |
| 課税所得 | 所得から、各種所得控除を差し引いた金額 |
このように、1年間で得た収入から、必要経費を差し引いたものを所得といい、この所得から各種控除を差し引いた金額を、課税所得といいます。
所得とは、税法における「もうけ」のことを意味しており、全部で10種類に分類されます。
これらの所得を集計し、納税額を計算して自ら申告・納税する手続きを「確定申告」というのです。
副業をするなら知っておきたい3つの所得

所得には、10つの種類があるとお伝えしましたが、副業をするうえで把握しておきたい所得は、次の3つです。
ここでは、上記3つの所得の詳しい内容をわかりやすく解説します。
事業所得
事業所得とは、その名のとおり、事業を営むことで得られた所得です。
事業とは、次の7つの分野に該当する業務のうち、生計を立てられる一定以上の規模において、「反復」「継続」「独立」して行われるものを指します。
このように、事業者自身がリスクを負いながら、上記に該当する業務を独立して経営することで得た収入から、必要経費を差し引いた金額を「事業所得」といいます。
参照:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
不動産所得
不動産所得とは、主に所有する不動産を貸し付けて得た所得のことであり、主に次の3つによって得た所得を指します。
具体的には、アパートやマンションなどの賃料や土地・建物の賃料を得ている場合や地上権など不動産の上に存する権利の設定と貸付けによって得た所得のことです。
参照:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁
雑所得
雑所得とは、事業所得や不動産所得を含む9種類の所得区分に該当しないその他の所得です。雑所得は、収入金額から必要経費を引いた金額を指します。
雑所得を大きく分けると、次の3つに分類されます。
副業による所得は、他の9種類の所得のどれにもあてはまらない所得全般として雑所得に該当するケースがほとんどです。主に、次のような副業は、雑所得として申告します。
副業における事業所得と雑所得の注意点

副業における事業所得と雑所得の線引きは、とても難しいポイントです。
ハンドメイドのアクセサリーを製作・販売をする場合、生計を立てられる規模である「事業規模」である場合は「事業所得」、趣味の作品として販売するようにお小遣い程度の稼ぎであれば、「雑所得」に該当します。
ここでは、副業における事業所得と雑所得の注意点をわかりやすく解説します。
副業の収入は事業所得として申告する方が有利
一見とても似た所得のように感じる雑所得と事業所得ですが、両者の明確な違いは「青色申告の適用の可否です。
青色申告とは、日々の取引を所定の帳簿に記載し、正しく申告をすれば、さまざまな特典を受けられる制度です。つまり、副業の収入を事業所得として申告すれば、雑所得では認められない税務上の特例を利用できます。
事業所得の主な特例として、次のようなものが挙げられます。
| 特例 | 内容 |
| 他の所得と損益通算できる | 本業で得た給与や賞与などから生じる給与所得から、事業所得で生じた損失を控除できる。 |
| 青色事業専従者給与 | 一緒に働く家族に支払う給与を青色事業専従者給与として経費として参入できる。 |
| 純損失の繰越し、繰戻し | 損益通算をしても赤字となる場合は、翌年以降3年間繰り越して、所得金額から控除できる。 |
| 青色申告特別控除 | 一定の要件を満たすことで、55万円(65万円)を所得から控除できる。要件を満たしていない場合も10万円の控除が適用される。 |
このように、事業所得として青色申告をすることで、さまざまな恩恵が受けられます。ただし、事業所得とするためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。
参照:No.2250 損益通算|国税庁
参照:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
参照:No.2070 青色申告制度|国税庁
青色申告の対象所得は限られている
青色申告ができるのは、次に挙げるいずれかの所得がある場合に限定されます。
上記に該当しない副業の収入を事業所得として申告したとしても、税務署が認めない恐れがあると覚えておきましょう。
開業届と青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告をするためには、事前に税務署から承認を受けなければなりません。
新規事業として副業を開始した場合は、開始した日から2ヵ月以内に税務署に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。また、承認申請にあたり事業の「開業届」の提出も求められます。
また、以前より継続している副業を青色申告に変更する場合は、青色申告を受けたい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出すれば、その年から適用されます。
副業でも事業所得に該当するケースもある
原則として、事業の売上で生計を維持している場合は「事業所得」、副業であれば「雑所得」に該当します。
事業所得と雑所得かどうかを判断するためには、主に次の3つの観点を総合的にチェックします。
具体的には、次のようなケースが事業所得に該当する可能性があります。
さらに、副業が「雑所得」「事業所得」、そして「不動産所得」に当てはまる場合は、必要経費が認められています。必要経費とは、収入を得るためにかかった費用のことです。副業の必要経費として認められる金額に上限は設けられていないため、雑所得や事業所得、不動産所得を得るために支出した費用であれば、経費として認められます。
雑所得として経費計上できる費用として、次のようなものが挙げられます。
帳簿の保存がない場合は雑所得になるケースもある
副業による所得を、雑所得ではなく事業所得とするためには、記帳や帳簿書類を保存しなければなりません。ただ、帳簿をつければ良いのではなく、保存も必要です。特に、最大65万円の特別控除である「青色申告特別控除」を適用するためには、帳簿作成・保存は必須です。
青色申告をするために必要な帳簿書類と保存期間は、次のとおりです。
| 帳簿書類 | 保存期間 | ||
| 帳簿 | 仕訳帳 総勘定元帳 現金出納帳 売掛帳 買掛帳 経費帳 固定資産台帳など | 7年 | |
| 書類 | 決算関係書類 | 損益計算書 貸借対照表 棚卸表 | 7年 |
| 現金預金取引等関係書類 | 領収証 小切手控 預金通帳 借用証 | 7年 (前々年分の事業所得および不動産所得の金額が300万円以下の場合は、5年) | |
| その他の書類 | 取引に関して作成し、または受領した上記以外の書類 請求書 | 5年 | |
本来は事業所得に該当するような副業であったとしても、上記のような帳簿をつけておかないと雑所得としてみなされてしまいます。必要な帳簿を把握したうえで、確実に作成・保存しましょう。
副業所得が20万円以下でも確定申告が必要となるケース

副業の所得が20万円以下であっても確定申告が必要となるケースは、次のとおりです。
それぞれのケースについて詳しく解説します。
所得税を納めすぎているケース
副業の収入が源泉徴収の対象となっており、あらかじめ報酬から源泉徴収額が差し引かれて、取引先が税務署に所得税を支払っている場合は、所得税を納めすぎている恐れがあります。その場合は、確定申告を行うことで税金が還付されるケースが多くあります。
また、会社員が副業としてパートやアルバイトとして給与収入がある場合でも、年末調整できるのは一社のみです。年末調整が実施されなかった勤務先の給与については、個人的に確定申告をすることで還付金を受けられる可能性があるでしょう。
住宅ローン控除や医療費控除を受けたいケース
住宅ローン控除や医療費控除などのように、年末調整の対象とならない所得控除・税額控除を受ける場合も、個人で確定申告を行うことで既に納めた所得税の還付を受けられる可能性があります。
この場合は、すべての所得を申告しなければならないため、副業所得が20万円だったとしても申告が必要です。
所得控除一覧
年末調整時に受けられる所得控除は、次のとおりです。
上記の所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。
副業の不動産経営が赤字となっているケース
副業として不動産経営をしている場合、経費を差し引くと赤字となるケースも珍しくありません。ローンの元本を経費として計上できないうえに、減価償却費が高額であるため、会計上赤字となる場合が多いためです。
給与所得がある場合は、「損益通算」によって所得税や住民税の節税につながるため、たとえ副業所得が20万円以下であったとしても確定申告をしましょう。
副業所得が20万円を超えて確定申告をしないとどうなる?

雑所得や事業所得などの副業所得が20万円を超えていても、経費を差し引いた残りの金額が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
ただし、副業の所得が20万円を超えているのにもかかわらず、確定申告をしない場合は、本来納めるべき税金が納付できないだけでなく、さまざまなデメリットが考えられます。
副業所得が20万円を超えて確定申告をしないことで、次のようなペナルティが科されます。
それぞれのペナルティの内容を詳しく解説します。
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告が期限内に行われずに期限後に申告した場合に課せられる附帯税のことです。
無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える場合は20%の割合で税金が加算されます。無申告加算税は、通知書が届いた翌日から1ヵ月以内に支払わなければなりません。
ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税の割合は5%まで軽減されます。さらに、申告期限から1ヵ月以内に自ら申告をして、納付すべき税額の全額を納めるべき期限である法定納期限までに納付の条件を満たすといった条件を満たすと、無申告加算税はかからないケースもあります。
延滞税
期限内に必要な税金が納付されない場合は、無申告加算税に加えて、延滞税が課税されます。
延滞税とは、納付期限までに税金を納めなかった場合に課税される附帯税のことです。
延滞税の税率は、原則として納付期限の翌日から2ヵ月以内までは7.3%、それ以降は14.6%となります。納税をするタイミングが遅くなればなるほど、課税額が増えるため、できるだけ早いタイミングで納税するように心がけましょう。
延滞税の割合に関する詳しい内容は、国税庁のホームページを確認してください。
重加算税
重加算税とは、税務調査によって確定申告が無申告であったり、事実と異なる内容で申告したり、さらには隠蔽したりなど、事実とは異なる内容で申告した場合に課せられる附帯税のことです。
重加算税の課税割合は、過少申告加算税や不納付加算税の代わりに35%、無申告加算税に代わって40%です。納付期限は、無申告加算税と同様に、通知書が届いた日の翌日から1ヵ月以内となるため注意しましょう。
参照:加算税の概要|財務省
副業による所得の計算方法

副業所得に対する正しい納税額を求めるためには、所得ごとに所得金額を計算しなければなりません。
ここでは、副業所得を計算する基本的な流れをわかりやすく解説します。
副業における所得の種類を確認する
所得区分には、給与所得をはじめ、事業所得や雑所得など、合計10種類があります。正しい納税額を割り出すためにも、まずはご自身の副業所得がどの種類に該当するのかをあらかじめ確認しておきましょう。
会社員の副業としてよく挙げられる所得として、次の4つがあります。
| 副業の内容 | 所得の種類 |
| パートやアルバイトなどの副業 | 給与所得 |
| 個人事業主としての事業活動による収入 | 事業所得 |
| 不動産の家賃収入 | 不動産所得 |
| 単発の原稿執筆やアフィリエイトなどのその他の収入 | 雑所得 |
繰り返しにはなりますが、副業における所得の種類は、主に「事業所得」、もしくは「雑所得」のいずれかに該当するケースがほとんどです。
所得区分がわからない場合は、国税庁のホームページを確認したり、税務署の問い合わせ窓口に相談したりしましょう。
所得金額や所得税額を計算する
所得税は、原則として次のような流れで計算していきます。
- 所得金額を求める
- 課税所得金額を求める
- 所得税の金額を求める
それぞれの項目について詳しくみていきましょう。
所得金額を求める
所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた利益のことです。雑所得や事業所得のように経費がある場合は問題ないものの、パートやアルバイトなどで副業している場合は、給与に経費は存在しません。その代わりとして、給与の金額に応じて一定の給与所得控除を給料から差し引き、給与所得金額を求めます。
ここでは、「給与所得」「事業所得」「不動産所得」、そして「雑所得」の所得金額の求め方を紹介しましょう。それぞれの所得金額の求め方は、次のとおりです。
給与所得金額=1年間の給与合計金額-給与所得控除
事業所得金額=売上-経費-青色申告特別控除(10万円または65万円)
参照:No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)|国税庁
不動産所得
不動産所得金額 = 売上-経費-青色申告特別控除(10万円または65万円)
参照:No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)|国税庁
雑所得金額=売上-経費
所得金額を求める際に必要なそれぞれの控除や経費に関する詳しい内容は、国税庁のホームページを参照してください。
課税所得金額を求める
所得を算出したら、各種所得控除を差し引いて、課税される所得金額を割り出します。
課税される所得金額の計算式は、次のとおりです。
所得控除とは、扶養する親族の人数やその年に支払った医療費など、納税者の生活状況に合わせて所得税の負担を軽減するための控除のことです。
所得税の金額を求める
課税所得金額に該当する所得税率をかけて、所得税の金額を求めます。
所得税の金額を割り出す計算式は、次のとおりです。
確定申告の際に記入する確定申告書にも、課税される所得金額という記入欄が設けられています。この金額に税率をかけて最終的な所得税の金額を求めていくのです。
日本の所得税では、累進課税制度が導入されており、課税される所得が高額になればなるほど税率も高くなります。
所得税の税率は、以下のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円以上194万9,000円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上329万9,000円未満 | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円以上694万9,000円未満 | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円以上899万9,000円未満 | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円以上1,799万9,000円未満 | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円以上3,999万9,000円未満 | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
住宅ローン控除のような税額控除がある場合は、求めた所得税の金額からさらに控除額を差し引いて申告することが可能です。
確定申告をすると会社に副業がバレる?

確定申告をする会社に副業している事実がバレてしまうのではないかと心配する人も多いでしょう。ここでは、確定申告をすると会社に副業がバレてしまう理由や副業禁止の勤務先にバレてしまうリスクについて解説します。
副業がバレてしまう理由
確定申告をして副業がバレてしまう理由として、住民税の金額が挙げられます。
会社の給与の場合、従業員が居住する市区町村から、住民税の金額の通知や納付書が会社宛に送付されます。副業で稼いだ分の税金は、翌年度の住民税に反映されるため、他の社員に比べて徴収される税額が高くなってしまうのです。
つまり、住民税の金額が自社の給与分よりも高額である場合、本業以外に何か副業しているのではないかを会社から疑われてしまうケースが考えられます。
副業禁止の勤務先にバレてしまうリスク
最近では、副業を認める会社も増えてきているものの、いまだに副業を禁止とする会社も一定数存在します。万が一、副業を禁止とする勤務先に副業している事実を知られてしまうと、就業規則違反として処分が科される恐れがあるでしょう。
注意や指導のみで終わるケースもあれば、懲戒処分を受けるケースもあるなど、会社によって処罰の内容は異なります。
勤務先に副業をしている事実を知られしまった場合は、なるべく早いタイミングで正直に打ち明けることが大切です。なかには、事前に相談することで副業を認めるケースもあるため、勤務先の副業ルールについて事前に調べておきましょう。
本業に副業の事実を知られないようにするための方法

本業の勤務先に副業している事実を知られないようにするための方法を紹介します。
普通徴収に変更する
副業が本業の勤務先に知られないようにするには、住民税の納税方法を「普通徴収」に変更することが大切です。
普通徴収とは、給与から天引きをせずに、自治体から送付される納税通知書に基づき、従業員自身が直接地方自治体に税金を納税する方法です。通常は、会社が従業員の給与から天引きする「特別徴収」によって住民税が支払われるケースがほとんどでしょう。
副業分の住民税を普通徴収に変更するだけで、副業の収入に関する住民税を勤務先に知られるリスクを回避できます。
普通徴収における住民税の支払い方
普通徴収によって副業の住民税を支払う場合は、確定申告後の6月中旬ごろに市区町村から住民税の納税通知書が郵送されます。住民税は、原則として6月、8月、10月、翌年1月の年4回にわたって納付が必要です。
銀行や郵便局の窓口、コンビニエンスストアでの支払いだけでなく、近年ではクレジットカード払いやスマートフォン決済アプリを利用した支払い方法に対応する自治体も増えています。お好みの支払い方法を選択し、納付書に記載された支払い期限を守って必要な税金を納めていきましょう。
副業も忘れずに確定申告をしましょう

副業とは、本業以外の仕事で収入を得ることです。会社員が副業する場合、副業の所得が20万円を超える場合に、原則として確定申告が必要です。
副業所得における確定申告を済ませないと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生する恐れもあります。副業で所得を得た場合は、申告する義務があるかを確認したうえで、期限内に確定申告の手続きを済ませましょう。