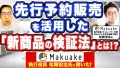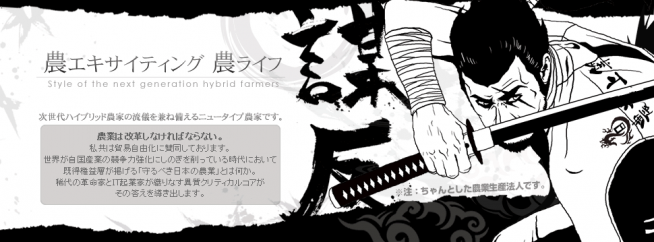報道や地域の告知物・集会所にあるのぼりなどで“こども食堂”という言葉を聞いたことがある人も少なくないのではないでしょうか。こども食堂は、家が貧困で食事ができない子どもだけが“ご飯を食べさせてもらいに行く場所”ではない。“誰でも行ける地域みんなの場所”だ。そこには、おじいちゃん・おばあちゃんと話す学生、その横で幼い子をかまう小中学生、キッチンでにぎやかに食事を作るお母さんたち、食事の準備を手伝うお父さんたち、というように縦・横の繋がりがある。
地域の人が、ただ集まって、みんなで食事をする。行かなくちゃいけないわけではなく、行きたいときに行ける“居場所”。そんな場所があることで、地域の人が“しがらみではない繋がり”を持つことができて、困っている人に手を差し伸べることもできると考える社会活動家の湯浅誠氏。こども食堂を切り盛りするのは、全国各地のボランティアや企業だが、湯浅誠氏はこども食堂が今以上に日本全国に増えるよう、資金や運営ノウハウの支援を行うべく、認定NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえを立ち上げたという。今回は、社会活動家の生き方をお伺いしてきました。
最初にボランティアをしたのは小学生。それが自然な環境でした

ーボランティアなどの支援活動を始められたきっかけは何でしたか?
大学入学時にはボランティアをしようと決めていました。
私の兄は障害者だったので、家にボランティアの人が来てくれる家庭で育ったということもあって、ボランティアに携わることは自然なことでした。
私が小学生だった1970年代は、障がい者の作業所というのが世の中に生まれ始めたばかりの頃で、まだ支援制度も何もなく、作業所の皆さんは自分たちで資金を作って運営していらっしゃった時代でした。障がい者が利用できるエレベーターを駅に設置してほしいと活動しているような頃です。私が住んでいた東京都・小平市に障がい者作業所のはしりとなる「あさやけ作業所」ができて、そこでは、運営資金を稼ぐために廃品回収をしていたんです。作業所の資金作りに協力してくれる家庭から、新聞の折り込みチラシを回収して回っては、それを売っていました。私も、トラックの脇について、回収した折り込みチラシを積み込む手伝いをしていましたよ。どういう経緯で、私がその活動に参加し始めたのかは覚えてないですけど、多分、両親も手伝っていたから一緒に行ったという感じじゃないですかね。
大学に入ってからは、児童養護施設でボランティアを始めました。ボランティアをしようと決めていたものの、何をしていいか分からなかったので、ボランティアセンターというところに「ボランティアをしたいんですけど、どうしたら良いですか?」って相談に行って、そこで、「学習ボランティアをしているところがあるから行ってみたらどうか」と、最初に紹介してもらって始めましたね。
大学院生時には増え続けるホームレスの支援に注力
―ご自身でもホームレス支援の団体を立ち上げられていますよね?ホームレス支援の団体はどうして設立されたんですか?
1995年の大学院に入る年にホームレス支援を始めまして、本腰を入れて活動するために1998年に支援団体を立ち上げました。
ホームレスの支援を始めた当時は、事務所で雑炊を作って寸胴鍋に入れて東京・渋谷にいたホームレスの人たちに配って回っていました。当時、東京・新宿に多くいたホームレスが社会的に注目されていて新宿でホームレス支援の活動をしている人はいたんですが渋谷にはいなかったので、我々は渋谷で始めました。
当時は路上での生活環境が厳しくて、段ボールで寝ているという人が圧倒的に多かったですね。1995年に100人だったホームレスが4年後には600人まで増えるというように、毎年どんどん増え続けていく感じでした。路上生活から抜けるのは簡単ではなくて、「仕事の話があった」と喜んで飯場(はんば ※1)に行く人もいるんですけど、多くの場合は劣悪な環境での仕事だったり、「一銭ももらえなかった」と言って路上生活に戻ってきたりする人もたくさんいる時代でした。
冬場は寒さで路上生活をしている人が亡くなってしまうという状況なので、我々は、命を守るために“テントを張ろう”と促しました。道端で寝るのとテントで寝るのと、状況は変わらないように思うかもしれませんけど、寝心地が全然違うんですよ。冬場は寒いので道端で寝ても2時間起きに目が覚めちゃうんですけど、テントを張って地面に“すのこ”を置いて、その上にブルーシートを敷いて寝ると、朝まで眠れるんですね。きちんと眠れないと日中、頭がボーッとするようになってしまって、仕事探しどころじゃないですし、ちょっとでも人間的な生活するためにも、やっぱりテントを張るしかないと思い、そういう活動を本格的にやり始めたのが1998年でした。
※1 主に工事現場など泊まり込みの労働現場