事業承継。
ゼロから会社を立ち上げる起業に対して、事業承継とは、既に存在する会社の経営権を引き継ぐことを意味します。
自ら起業した会社を経営することと、既に社員もいて事業が運営されている会社の経営を引き継ぐことでは、同じ「経営」という仕事でも求められる能力が異なります。
今回お話を伺ったのは、株式会社ウィズテック代表の日向亮介さん。
株式会社建設システムの社員として働いていた日向さんは、2022年にグループ会社である株式会社ウィズテックの代表に就任しました(現在はウィズテックの代表と建設システムの社員を兼務)。
今回はそんな日向さんが運営する事業、そして会社を引き継ぐことの苦労と面白さについて伺いました。
日向亮介さん
株式会社ウィズテック 代表取締役社長
建設業向けのソフトウェアを開発する、株式会社建設システムに入社。営業、採用、プロモーション、コンタクトセンター、総務など様々な部署を経験した後、経営企画やブランディング、新規事業の立ち上げを経験する。
2022年3月、同社関連会社の株式会社ウィズテックの代表取締役社長に就任。現在はウィズテックの代表と建設システムの社員を兼務している。
SES事業を展開していたウィズテック。日向さんが代表就任後にオンライン教育事業を始めた理由

――日向さんが代表を務められている、株式会社ウィズテック(以下、ウィズテック)の事業内容について、まずは簡単にお聞かせください。

エンジニアと企業をマッチングし、技術支援を行うSES事業(※)を行っています。加えて2023年8月からは、企業向けのオンライン教育事業をスタートさせました。
現在はこの2つの事業を軸に、運営しています。
※システムエンジニアリングサービスの略称
――全く方向性の異なる事業ですね。

はい。前者のSES事業は以前から行っていたもので、後者のオンライン教育事業は私が代表になってから立ち上げたんです。
――ウィズテックは日向さんが創業社長というわけではないのですね。経緯を教えていただけますか?

元々私はウィズテックのグループ会社である、株式会社建設システムで働いていました。そして2022年3月にウィズテックの代表に就任したんです(現在も建設システムの社員を兼務)。
代表になる前は、営業や採用をはじめ、様々な部署の業務を経験してきました。やがて経営企画の業務や新規事業の立ち上げを経て、起業に興味を持つようになったんです。
――起業に興味を持った理由というのは?

やはり自分自身が経営者の立場にならなければ、本当の意味で経営企画の仕事を理解することはできないなと痛感していたんです。
そんな矢先に、まだ立ち上げて間もなかったウィズテックの代表に就任し、実際に経営の仕事をさせていただけることになりました。
まずは既存のSES事業に力を入れつつ、オンライン教育事業を新たにスタートさせました。
というのもこの事業は、私が会社員時代に経験してきた中で、特に挑戦してみたい領域のうちの1つだったんです。
――なぜオンライン教育事業に挑戦してみたいと思ったのでしょう?

きっかけは実際に会社で採用関係の仕事をしてきた中で、新卒採用や第二新卒、中途採用者のMicrosoft Officeの修練度に、かなり個人差があるなと感じていたからです。
Microsoft Officeの基本的な操作は、今やオフィスワーク系のビジネスパーソンにとって、必須のスキル。
仕事をする上での「共通言語」とも言うべきこのスキルを、一定のラインまで上げておくことは、今後の会社での仕事を円滑に進める上でも重要ですし、ひいては従業員の定着率にも大きく関わるなと感じていました。
そこでウィズテックでは新たに、Microsoft Officeの基本的な扱い方を、e-ラーニングやオンライン授業を通して、社員の方に受講していただく事業を立ち上げたんです。
今あるカードの中で一番いい戦い方を探る。事業承継をする上で大切なこと

――グループ会社の経営者として抜擢される形で、ウィズテックの社長就任から1年半以上が経ちますが、振り返ってみていかがでしょうか?

本音を言うと、とても大変でした(笑)。
何より「既に働いている従業員の生活を守ること」の重圧と、その責任に対する覚悟を自分の中で決め切るまでが特にしんどかったですね。
一概に比較はできませんが、もういっそのこと「自分の力でゼロから起業した方がラクだっただろうな」と感じる瞬間すらあったほどです。
――経営を引き継ぐことはある意味、自分で会社を立ち上げる以上の重圧があると。

そうですね。やはり経営者には従業員を守る責任があるので。
さらにSESという事業の性質上、エンジニアという人材を採用して増やさないことには、会社も大きくできません。
会社を大きくするために、人を採用して増やす。すると当然、守らなければならない人も増える……という循環に、最初の頃は正直戸惑いもありました。

――日向さんはどのようにその重圧を乗り越えていったのでしょう?

2つ、行ったことがあります。
1つ目はいきなり精神論になってしまい恐縮なのですが……覚悟を決めること、でしたね。
経営という仕事への重圧を感じたのも事実ですが、それ以上にこの会社をもっといい会社にしたいという気持ちも強かったんです。
だから重圧に負けて、頭の中であれこれと不安に駆られている場合じゃないなと。何よりもまず、腹を括るところから始めようと思いました。
――もう1つはなんでしょう?

今の会社を取り巻く状況をあらゆる角度から分析しました。まだ小さい会社だからこそ、人もお金といったリソースも限られてきます。
しかし、必ずその中に戦える武器やヒントになるものがあるだろうと信じて、代表に就任してすぐ、メンバー全員と1on1のミーティングを実施しました。
そして、1人ひとりの適性と長所が最大限発揮される環境や戦い方を模索することにしたんです。この点に関しては、会社員時代にマネジメントの経験があったこともあり、自然と行えましたね。
腹を括って冷静になって、そして今あるカードの中で一番良い勝ち方を探っていく。組織を経営するにあたって大切なことは、結局そこに尽きるのかなと感じています。
責任や重圧の先にある、経営の楽しさとやりがい

――大変だとおっしゃる割に、日向さんがとても楽しそうにお話しされているのが印象的です。

ありがとうございます。
ここまで大変だったことを赤裸々に語ってきてしまいましたが……正直言うと、この「大変さ」を楽しんでいる自分もどこかにいるんです(笑)。
経営ってもちろん「大変」なんですけど、少しずつだったとしても、自分や会社、メンバーが前に進んでいるような感覚があるんですよね。
それがやりがいというか、楽しいところなんですよ。責任や重圧の先にあるものを、これからも見ていけるように頑張りたいと思います。
――最後に、読者の方へメッセージをお願いします。

独立・起業にもたくさんの種類があります。
自分でゼロから事業を立ち上げる人もいらっしゃれば、私のように誰かの運営していた事業を引き継ぐ形で独立する人もいます。
独立・起業を考えるなら、ぜひ自分に合った形を選んでいただきたいですね。そのために、まずは小さなところから挑戦してみることをお勧めします。
例えば、会社員をしながら副業を始めてみるのもいいですし、会社に在籍しながら新規事業を立ち上げるのもいいかもしれません。あるいは、部署異動や部署を兼務するなどしてもいいでしょう。
要するに小さくてもいいので、これまで自分がやったことのないことに、積極的に挑戦する習慣を身につけることが大切だと思います。
仕事における挑戦とは「培ってきたキャリアを手放すこと」と言い換えることもできます。
将来的に独立・起業を考えるなら、このキャリアを小さく手放すところから始めてみるといいのではないでしょうか。
取材・文=内藤 祐介

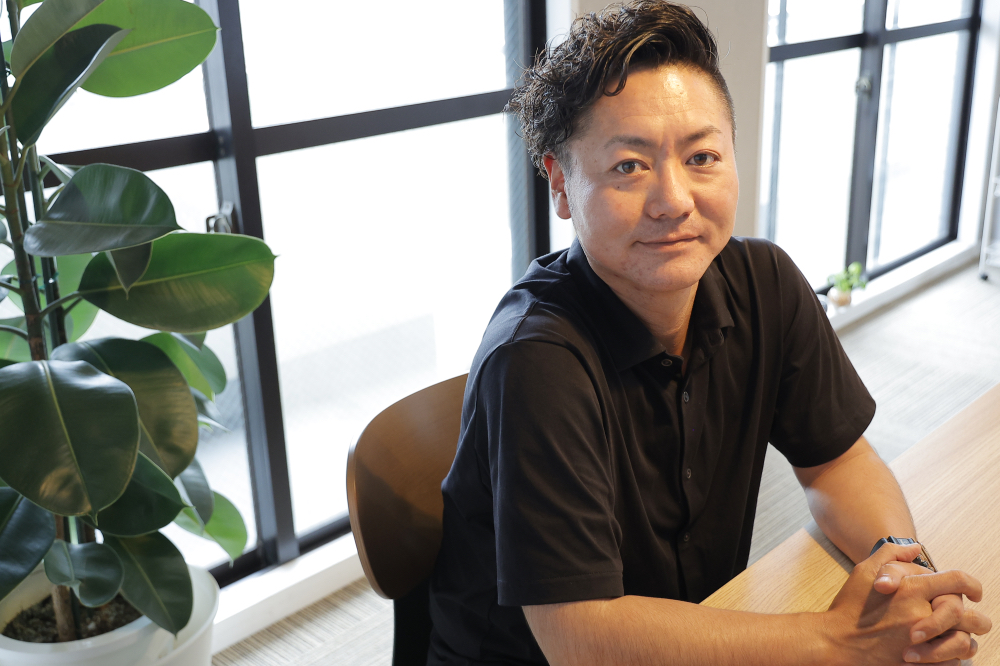
















 独立、開業、起業をご検討のみなさまへ
独立、開業、起業をご検討のみなさまへ