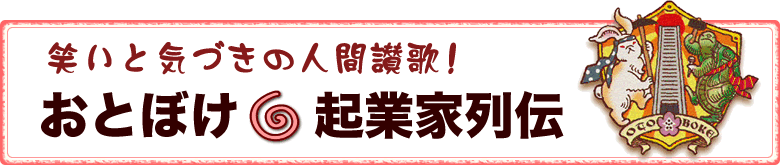

東京をライバル視する大阪人が減った。東京人が右だと言えば、無条件に左だと言い張るのが大阪人の真骨頂だと思っていたが、どうも最近の大阪人は協調精神に富んでいる。というよりも、日本中をのみ込んでいく「東京的な何か」が、とうとう大阪をも浸蝕しはじめたということかもしれない。
せんだって大阪市で講演した際、「大阪は今後どうしたらいいんですか?」という質問が出た。「変えるべきは変える。守るべきは守ればいい。で、あなたは何が守るべき大阪の魅力だと思いますか?」と反問してみた。質問者は一瞬間を置いてから「お笑いやと思います」と答えた。回答の内容はいいと思う。だが回答の仕方がイマイチだ。正しいだけなら、それはまさに「東京的な答え」である。
できれば大阪の将来を背負って立つ若者には、「お笑いやと思います。大阪人は人を笑わせるのが得意です。僕は笑われるのが得意ですけど(笑)」くらいは最低でも言ってほしい。要するに余計なことを言ってほしい。普通言わないことまで言うからおかしいのだし、そこに自虐ネタが入ったり、韻を踏んだ言い回しがあったりすると、聞いたほうは笑いやすくなる。笑いの提供とは、笑いたいと思っている(顕在的だろうと潜在的だろうと)相手が、堂々と笑えるための材料を提供してあげるということだ。
その点、抜かりがないのがカナッペ。例えば『アントレ』の特集記事用の写真撮影の時。「社長、ニッコリでお願いしまーす」と編集者(私のこと)。「オッケー。今日は乗ってるよアタシー。よーし、脱いだろ」(と、スーツのボタンに手を掛ける)といった具合である。当然、関係者一同爆笑。一息入れて次は違う角度からの撮影。
「社長、そしたらセミヌードいきます」と私もボケる。「ええよ」(と、ボタンをひとつかふたつはずしつつ)「しもた。今日の下着、ババシャツやった〜」と彼女。またまた大爆笑。こうしてスタッフたちをリラックスさせ、仕事を円滑に進めていくのだ。
大阪隣県で生まれ、大阪で育って、大阪のエンターテインメント企業に勤めた後に起業した彼女にとって、この程度の「笑い」は呼吸をするのと同じくらい自然な行為だと思う。「カナッペのボケは本当に一流だよね」と褒めたら、「それをビジネスに生かせないことにおいても一流やねん(笑)」とすかさず答える。やはり大阪人だ。
しかしながら、その当時の彼女は、その大阪的な能力を事業に生かすことが本当にできず、悶々とする日々を送っていたのである。企業の広報物を制作するのがカナッペの会社の事業なのだが、こういった仕事は顧客の意向が強く働くから、彼女のセンスがそっくりそのまま価値を生み出すということにもならない。
カナッペは決断した。制作会社の経営を仲間たちに譲り、「大阪人的な笑いを取り入れたコミュニケーション能力向上のための研修」を手がける会社を新たに起こしたのである。彼女ならではの事業だ。ただし、それを大阪でやったのでは光らない。かくして彼女は拠点を東京に移すことにした。結果的にそれは当たった。
彼女から東京進出の決意を聞かされた時、私の頭はすぐに名曲『大阪で生まれた女』を奏ではじめた。大阪を出られない。でも、大阪を出よう。イヤでも歌詞と現実がダブってくる。ちなみにこの曲の歌詞、実は18番まである。長編だ。萩原健一さんや河島英五さんが歌ってヒットさせたのはそのうちの4番と6番を中心にしたショートバージョン。ネットで検索すればおそらく全歌詞を知ることができるだろう。たとえば7番の歌詞では「ひかり32号」に乗って東京へ向かった「女」が、「大阪にも夢はあった」「大阪にも愛はあった」と後ろ髪を引かれる思いを口にしている。その心中が容易に想像できて胸が熱くなる。カナッペの心のうちもきっと同じだったろう。
「増田さん、何ゆーてるの? 東京進出ゆーても東京と大阪を行ったり来たりするだけやで。歌みたいなロマンチックな話やあらへんわ〜(笑)」だってさ。感動して損した。
一説によれば大阪の海は悲しい色をしているらしい。その色を内側に抱きかかえているから大阪の笑いは素敵なのだ。愛されるのだ。大阪人よ、くれぐれも東京的になるなかれ。ひとつよろしくお願いします。
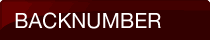

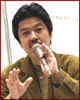
1959年生まれ。87年、株式会社タンク設立。97年、「アントレ」創刊に参加。以降、同誌編集デスクとして起業・独立支援に奔走。講演やセミナーを通じて年間1000人以上の経営者や起業家と出会い、アドバイスと激励を送り続けている。現在、(社)起業支援ネットワークNICeの代表としても活躍中。また、中小企業大学校講師、(財)女性労働協会講師、ドリームゲート「事業アイデア&プラン」ナビゲーター、USEN「ビジネス実務相談」回答者なども歴任。著書に『起業・独立の強化書』(朝日新聞社)、『正しく儲ける「起業術」』(アスコム)。ほか共著も多数。