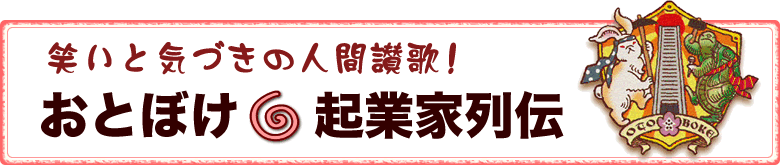
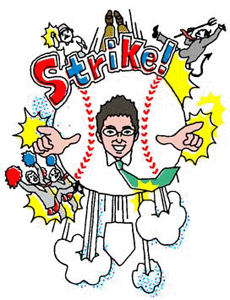
中学生まで天才投手として名をはせていた清原和博は、進学したPL学園で桑田真澄に遭遇し、エースとして生きる道を断念した。「上には上がいる」を示す好例としてよく語られる話である。時を同じくして中国地方の中山間地の小さな高校でも2人のエースがしのぎを削っていた。むろんこっちは誰も知らない超ローカルネタである。
そのローカルコンビのひとりが今や我が盟友となったシゲヤンだ。結局その時のシゲヤンはライバルの投じる速球にはかなわないと判断し、清原のように打撃に活路を求めたか……というと、そうではなかった。「スピードボールで勝てないなら変化球だ」。
あくまで投手にこだわったシゲヤンに、ようやく登板チャンスがめぐってきたのは、甲子園出場をかけた県予選の1回戦だった。
血のにじむような練習で磨き上げた変化球。「打てるものなら打ってみろ!」。シゲヤンの青春のすべてをのせた一球は、「打てるものなので打ってみた」と打者がコメントしたかどうかはわからないが、いとも簡単にヒットされた。その瞬間、シゲヤンの高校最後の夏が終わった。KKコンビが甲子園をわかせている頃、アロハにサングラスという、にわかチンピラスタイルで村の盆踊り大会会場入り口付近にたむろすシゲヤンは、もう野球のことなどまったく忘れてひたすら女子の物色に励んでいた。
この男、今でもそうで、「済んでしまったことをクヨクヨしない能力」が異常なまでに高い。私が過去のミスを詫びた時、「えっ? そんなこと、あったっけ?」と流してくれたので、てっきり器の大きい人間だと思って尊敬していたのだが、反対に彼のミスを私がとがめた時も「えっ? そうだっけ?」なのだ。クヨクヨしないどころか、覚えてすらいない。切り替えの達人なのかもしれない。
そういうわけで、野球への未練は微塵もない彼だが、「痛恨の一球」は彼のその後の人生観を大きく左右したそうだ。「勝負は真っすぐに限る。正面からぶつかって負ければ納得がいく。かわそうとして負けたら悔いが残る」と。わかる気がする。
わかるが、現実には多少の駆け引きや手練手管が必要なものである。だが、シゲヤンは本当にストレート一本勝負だ。そんな生き方で大丈夫かと心配になるが、大丈夫だ。雑誌編集長を辞して設立した出版社も4年目になるが、出版不況にもかかわらず、着実にヒット作を世に送りだしている。変化球だらけの世にあっては、ストレートのほうがむしろ効果的なのかもしれない。むろん彼にそんな計算はない。
ちなみにでき上がってきた本のデザインに「納得がいかない」と、自腹で何百万円も出してまるまる本をつくり直したこともある。真っすぐというより、もはや愚直だ。
ただ、自分に傷が付くことを恐れない人間の言い分にはやはり威力がある。彼とはかれこれ10年以上の付き合いだが、彼の発する正論が、権謀術策をめぐらす人々を撃破したり、沈滞する集団をよみがえらせたりするシーンを私は何度も目にしてきた。彼は正しいと信じたことを絶対に疑わないのだ。ストレート一本人生を決意させたのは「痛恨の一球」だが、それを何十年も支えているのは、この「疑わない力」だ。
しかし何事にも程がある。誰が聞いたって、「そんなのウソに決まっているでしょ」といった類の話まで、シゲヤンは疑わない。信じたら最後、絶対に疑わない。
「驚いたんだけどさ、精液を冷凍保存して食べる女性が増えているらしいよ。美肌効果があるんだって」。そんな女が増えているわけはない(笑)。だいたい増えたかどうかなんて、誰がどうやって調べたっていうの? 聞けば飲み屋のママから仕入れた話だという。典型的な飲み屋ネタなのに、彼はかたくなに真実だと思っている。まあ、彼のことだから、そんな話題を口にしていたこともやがては忘れてしまうんだろうが。
その昔、私と彼は互いの役割について語り合い、まっとうすることを誓い合った。「増田はあの手この手で人々に食い込む。シゲヤンは大所高所から正論をぶちかます」。そんな約束を交わした友、だから盟友なのだが、たぶん彼はその言葉も忘れているだろう。だが何の問題もない。約束は覚えていることが大事なのではなく、果たすことが大事だからだ。もっともそんな約束などしなくても、彼はそうする人間だ。
互いが間違いなく遂行できる事柄を約束する。そうすれば友は決して裏切らない。
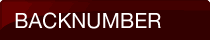

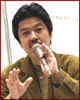
1959年生まれ。87年、株式会社タンク設立。97年、「アントレ」創刊に参加。以降、同誌編集デスクとして起業・独立支援に奔走。講演やセミナーを通じて年間1000人以上の経営者や起業家と出会い、アドバイスと激励を送り続けている。現在、(社)起業支援ネットワークNICeの代表としても活躍中。また、中小企業大学校講師、(財)女性労働協会講師、ドリームゲート「事業アイデア&プラン」ナビゲーター、USEN「ビジネス実務相談」回答者なども歴任。著書に『起業・独立の強化書』(朝日新聞社)、『正しく儲ける「起業術」』(アスコム)。ほか共著も多数。